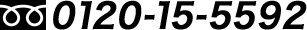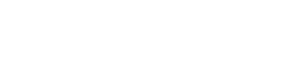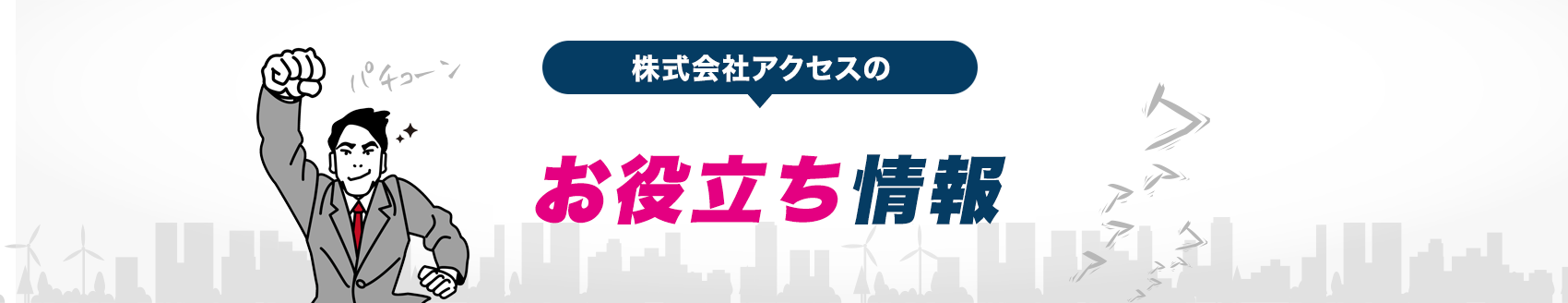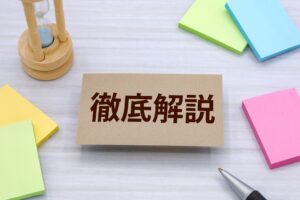採用担当に向いている人の特徴9選
企業の成長を左右する重要な役割を担う採用担当者ですが、誰でも適性があるわけではありません。
採用活動は企業の未来を創る人材を選ぶ仕事であり、その成否は採用担当者の資質に大きく左右されます。
近年、採用市場は売り手市場が続いており、優秀な人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。
このような環境下で、適切な人材を見極め、自社の魅力を効果的に伝え、入社まで丁寧にフォローできる採用担当者の存在が、企業の競争力を大きく左右するのです。
しかし、採用担当者に求められる資質やスキルは多岐にわたり、どのような人材を採用担当に配置すべきか悩んでいる経営者や人事責任者も多いのではないでしょうか。
コミュニケーション能力が高ければ良いのか、論理的思考力が必要なのか、それとも別の要素が重要なのか。
本記事では、採用担当に向いている人の特徴を9つの観点から詳しく解説していきます。
採用担当の役割や求められる姿勢から始まり、具体的なスキルや適性、さらには向いていない人の特徴や人選のコツまで、採用担当者を選ぶ際に必要な情報を網羅的にお届けします。
これから採用担当を任命しようと考えている方、自身が採用担当として適性があるか知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
CONTENTS
採用担当の役割と基礎知識

主な業務範囲(計画〜選考〜内定者フォロー)
採用担当の業務は、採用計画の立案から内定者フォローまで、非常に幅広い範囲に及びます。
まず、採用活動のスタート地点となるのが採用計画の策定です。
経営層や各部署の責任者と連携しながら、どのポジションに何名の人材が必要か、どのようなスキルや経験を持った人材を求めるかを明確にしていきます。
この段階では、事業計画や組織戦略を理解し、中長期的な視点で人材ニーズを予測する力が求められます。
次に、採用手法の選定と実行に移ります。
求人広告の掲載、人材紹介会社の活用、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用など、複数の採用チャネルから最適な手法を選択し、予算内で効果的に運用する必要があります。
求人原稿の作成では、職務内容や求める人物像を分かりやすく表現し、自社の魅力を効果的に伝えるライティングスキルも必要です。
応募者が集まり始めると、選考プロセスの運営という重要な業務が始まります。
書類選考では、応募書類から候補者の適性や経験を正確に見極め、次のステップに進むべき人材を選別します。
面接の日程調整では、候補者と面接官双方のスケジュールを調整し、スムーズな選考フローを実現しなければなりません。
面接当日は、候補者を温かく迎え入れ、リラックスして本来の力を発揮できる環境を整えることも採用担当の重要な役割です。
面接では、的確な質問を通じて候補者の能力や適性、価値観を深く理解するとともに、企業の魅力や職務の詳細を丁寧に説明します。
単なる評価者ではなく、候補者と企業の双方向のコミュニケーションを促進するファシリテーターとしての役割が求められるのです。
選考が進むにつれて、合否判断のための情報整理や、経営層・現場責任者への報告も必要になります。
各候補者の評価をまとめ、データに基づいた客観的な判断材料を提供することで、採用の質を高めることができます。
内定を出した後も、採用担当の仕事は終わりません。
むしろ、内定者フォローは採用活動の中で最も重要な局面の一つといえるでしょう。
内定承諾から入社までの期間は数ヶ月に及ぶことも多く、その間に内定者の不安を解消し、入社へのモチベーションを高めていく必要があります。
定期的な連絡、会社見学や懇親会の企画、先輩社員との交流機会の提供など、きめ細かなフォローを通じて内定辞退を防ぎ、入社後の活躍につなげるのです。
さらに、採用活動全体の効果測定や改善提案も採用担当の重要な業務です。
各採用チャネルからの応募数や採用率、選考通過率、内定承諾率などのデータを分析し、次回の採用活動に向けた改善点を洗い出すことで、継続的に採用力を高めていきます。
このように、採用担当の業務範囲は非常に広く、それぞれの段階で異なるスキルや適性が求められる複雑な仕事なのです。
「会社の顔」として求められる姿勢(信頼・誠実)
採用担当者は、**候補者にとって企業との最初の接点であり、まさに「会社の顔」**として機能します。
候補者が企業に対して抱く第一印象の多くは、採用担当者との関わりを通じて形成されるのです。
そのため、採用担当者の言動や姿勢は、企業のブランドイメージに直結する重要な要素となります。
まず求められるのが、信頼を築くための誠実な姿勢です。
採用活動では、候補者に対して企業の良い面を積極的にアピールすることが必要ですが、事実と異なる情報を伝えたり、都合の悪い情報を隠したりすることは絶対に避けなければなりません。
たとえば、残業時間について質問された際に、実態よりも少なく伝えたり、曖昧な表現でごまかしたりすれば、入社後のミスマッチや早期離職につながります。
誠実に事実を伝えることで、候補者は正確な判断材料を得られ、入社後のギャップを最小限に抑えることができるのです。
また、約束を守ることも信頼構築の基本です。
「○日までに選考結果をお知らせします」と伝えたら、必ずその期日を守る必要があります。
万が一遅れが生じる場合は、事前に連絡を入れ、理由と新しい期日を明確に伝えることで、候補者の不安を解消できます。
小さな約束を一つひとつ守ることが、企業への信頼感を醸成していくのです。
次に重要なのが、候補者一人ひとりを尊重する姿勢です。
採用活動では多くの応募者と接するため、業務が流れ作業になってしまうこともあります。
しかし、候補者にとっては人生の重要な転機であり、一人ひとりが真剣に就職や転職を考えていることを忘れてはなりません。
不採用の連絡であっても、丁寧で思いやりのある対応を心がけることで、候補者は企業に対して良い印象を持ち続けることができます。
実際、不採用となった候補者が後に顧客になったり、別の優秀な人材を紹介してくれたりするケースも珍しくありません。
さらに、公平性と透明性を保つ姿勢も欠かせません。
採用選考では、性別、年齢、国籍、学歴などによる差別は法律で禁止されています。
すべての候補者に対して平等な機会を提供し、能力や適性に基づいた公正な評価を行うことが採用担当者の責務です。
また、選考基準や選考プロセスを明確にし、候補者に対して透明性の高い情報提供を行うことで、納得感のある選考を実現できます。
加えて、迅速かつ丁寧なコミュニケーションも信頼構築には不可欠です。
候補者からの問い合わせや質問には、できる限り早く、かつ丁寧に対応する必要があります。
返信が遅れると、候補者は「自分は重視されていないのではないか」「この企業は対応が遅いのではないか」という不安を抱きます。
特に選考中の候補者は他社の選考も並行して受けていることが多く、迅速な対応が優秀な人材の確保につながるのです。
最後に、プロフェッショナルとしての姿勢を常に保つことが重要です。
身だしなみ、言葉遣い、メールの文面、電話での対応など、あらゆる場面で企業の代表としてふさわしい振る舞いを心がける必要があります。
候補者は採用担当者の言動から、その企業の文化や価値観を読み取ろうとしていることを忘れてはなりません。
このように、採用担当者は単に選考を進行させるだけでなく、企業の顔として信頼と誠実さを体現する存在であることが求められるのです。
採用担当に向いている人の条件

高いコミュニケーション力(傾聴・説明・交渉)
採用担当に最も求められる能力の一つが、高いコミュニケーション力です。
ただし、ここで言うコミュニケーション力とは、単に話が上手いことや社交的であることを意味するわけではありません。
採用活動に必要なコミュニケーション力は、傾聴力、説明力、交渉力という3つの要素で構成される、非常に専門的なスキルなのです。
まず、傾聴力は採用担当者にとって最も基本的かつ重要な能力といえます。
面接では候補者の話をじっくりと聞き、その人の経験やスキル、価値観、キャリアビジョンを深く理解する必要があります。
表面的な情報だけでなく、言葉の背後にある本音や動機、潜在的な能力を引き出すことが求められるのです。
優れた傾聴力を持つ採用担当者は、候補者が話しやすい雰囲気を作り出し、適切な質問や相槌を通じて対話を深めていきます。
「それはどういう意味ですか」「具体的にはどのような状況でしたか」といった掘り下げる質問を投げかけることで、候補者の真の適性や可能性を見極めることができるのです。
また、候補者の非言語コミュニケーション、つまり表情や声のトーン、姿勢なども注意深く観察することで、より深い理解につながります。
次に重要なのが、説明力です。
採用担当者は、企業のビジョンやミッション、事業内容、職務の詳細、待遇や福利厚生、キャリアパスなど、多岐にわたる情報を候補者に分かりやすく伝える必要があります。
特に重要なのは、候補者の関心や疑問に合わせて、適切な情報を適切なタイミングで提供する能力です。
たとえば、キャリアアップに強い関心を持つ候補者には成長機会や研修制度を詳しく説明し、ワークライフバランスを重視する候補者には柔軟な働き方や休暇制度を具体的に伝えるといった対応が求められます。
また、複雑な情報を分かりやすく整理して伝える力も必要です。
専門用語や社内用語を多用せず、候補者の立場に立って理解しやすい言葉で説明することで、企業の魅力を効果的に伝えることができます。
さらに、ストーリーテリングの手法を活用し、実際の社員の成功事例や企業の成長ストーリーを交えて説明することで、候補者の共感を引き出すことも可能です。
そして、交渉力も採用担当者には欠かせない能力です。
内定を出した後、候補者との条件面での調整が必要になることは少なくありません。
給与、勤務地、入社時期など、さまざまな条件について候補者と話し合い、双方が納得できる着地点を見つける必要があります。
優れた交渉力を持つ採用担当者は、一方的に企業の条件を押し付けるのではなく、候補者のニーズや事情を理解した上で、Win-Winの関係を築くための提案を行います。
たとえば、給与面で完全に希望に添えない場合でも、リモートワークの頻度を増やす、研修制度を充実させる、早期のキャリアアップの機会を提示するなど、別の価値を提供することで全体としての魅力を高めるアプローチが有効です。
また、交渉では社内の関係者とも調整が必要になります。
経営層や配属先の責任者に対して、候補者の価値や市場の状況を説明し、条件面での柔軟な対応を引き出すこともあります。
このように、社内外の多様なステークホルダーとの円滑なコミュニケーションを実現できる人材が、採用担当として活躍できるのです。
加えて、書面でのコミュニケーション力も見落とせません。
メールでのやり取りや求人原稿の作成、社内報告書の作成など、文章を通じて正確かつ分かりやすく情報を伝える能力が求められます。
特にメールでは、簡潔でありながら必要な情報を漏れなく記載し、相手に配慮した表現を使うことで、良好な関係を築くことができます。
以下のような場面で、コミュニケーション力が具体的に発揮されます。
- 面接で候補者の本音を引き出す質問をする場面
- 企業の魅力を候補者の関心に合わせて説明する場面
- 内定条件について候補者と調整する場面
- 不採用の連絡を丁寧かつ前向きに伝える場面
- 社内の関係者に選考状況を分かりやすく報告する場面
このように、採用担当には多面的なコミュニケーション力が求められ、これらを高いレベルで実践できる人材が向いているといえます。
論理的思考と客観性(データに基づく判断)
採用担当には、論理的思考力と客観的な判断力も不可欠です。
感覚や直感だけで採用活動を進めると、ミスマッチや採用ミスのリスクが高まり、企業に大きな損失をもたらす可能性があります。
まず、論理的思考力が求められる場面について見ていきましょう。
採用計画を立てる段階では、事業計画や組織の現状を分析し、どのポジションにどのような人材が何名必要かを論理的に導き出す必要があります。
たとえば、新規事業の立ち上げに伴い営業部門を強化する場合、売上目標から逆算して必要な営業担当者数を算出し、さらに各担当者に求められるスキルレベルを定義していきます。
このプロセスでは、根拠のある数値計画を立てる論理的思考力が不可欠です。
選考プロセスでも論理的思考力が活きてきます。
候補者の経歴やスキル、面接での回答内容を体系的に整理し、求める人材像との適合度を論理的に評価する必要があります。
「この候補者は営業経験が5年あり、目標達成率も平均120%を記録している。さらに新規開拓に強みがあり、当社が求める開拓型営業のスキルセットにマッチする」といった具合に、事実に基づいた論理的な評価を行うのです。
また、データに基づく客観的な判断力も採用担当の重要な資質です。
採用活動では膨大なデータが発生します。
応募者数、書類選考通過率、面接通過率、内定承諾率、採用チャネルごとの効果、採用単価など、これらのデータを正確に分析し、改善につなげる能力が求められます。
たとえば、ある求人サイトからの応募数は多いものの選考通過率が低いというデータがあった場合、求人原稿と実際の求める人材像にズレがある可能性を論理的に推測できます。
逆に、応募数は少ないものの採用率が高いチャネルがあれば、そこに予算を重点配分するといった戦略的判断が可能になります。
採用担当に向いている人は、以下のような分析を日常的に行います。
| 分析項目 | 目的 | 具体的な活用方法 |
| 採用チャネル別の応募数・採用率 | 効果的なチャネルの特定 | 予算配分の最適化 |
| 選考段階ごとの通過率 | ボトルネックの発見 | 選考プロセスの改善 |
| 内定承諾率 | 競合との比較優位性の把握 | 条件面や魅力付けの見直し |
| 採用単価の推移 | コスト効率の評価 | 採用手法の見直し |
さらに、主観を排除した公平な評価も重要です。
人間は無意識のうちにバイアス(偏見)を持ってしまうものです。
「この大学出身者は優秀だろう」「若い方が伸びしろがあるだろう」といった先入観を排除し、客観的な事実とデータに基づいて評価する姿勢が求められます。
そのために、採用担当に向いている人は評価基準を明確に定め、複数の評価者で判断する仕組みを作るなど、客観性を担保する工夫を行います。
また、自分自身の判断に対しても批判的に検証する姿勢を持っています。
「なぜこの候補者を高く評価したのか」「その判断は感覚的なものではないか」「データや事実で裏付けられているか」と、常に自問自答しながら判断の質を高めるのです。
加えて、仮説検証のサイクルを回す能力も論理的思考力の一部です。
「この求人原稿の表現を変えれば応募数が増えるのではないか」という仮説を立て、実際に変更してデータを取り、結果を検証する。
このようなPDCAサイクルを回すことで、継続的に採用活動の質を向上させることができます。
論理的思考と客観性を持つ採用担当者は、以下のような行動をとります。
- 候補者の評価を事実とデータで説明できる
- 採用活動の改善提案に根拠を示せる
- 感情や第一印象だけで判断しない
- 複数の選択肢を比較検討して意思決定する
- 自分の判断ミスを認め、改善につなげる
このように、論理的に考え、データに基づいて客観的に判断できる人材が、採用担当として成果を上げることができるのです。
成果に直結する実務スキル

調整力・プロジェクト管理力(社内外の日程/情報連携)
採用活動は、複数のステークホルダーが関わる複雑なプロジェクトです。
そのため、採用担当には高度な調整力とプロジェクト管理力が求められます。
まず、日程調整力は採用担当の基本的かつ重要なスキルです。
採用活動では、候補者、面接官、会議室、場合によっては外部の面接会場など、多くの要素を調整する必要があります。
特に中途採用では、候補者が在職中のケースが多く、限られた時間枠の中で面接日程を確保することが求められます。
優れた調整力を持つ採用担当者は、候補者の都合を最優先しながらも、社内の面接官のスケジュールを効率的に確保します。
複数の候補者の面接を同日にまとめて設定することで面接官の負担を軽減したり、オンライン面接を活用して日程調整の柔軟性を高めたりする工夫を行います。
また、急な日程変更にも柔軟に対応できる予備日を確保しておくなど、リスクマネジメントの視点も持っています。
次に、情報連携力も極めて重要です。
採用活動では、候補者情報、選考状況、評価結果など、多くの情報を社内の関係者と共有する必要があります。
経営層、配属予定部署の責任者、人事部門内のメンバー、そして面接官など、それぞれに必要な情報を適切なタイミングで正確に伝えることが求められます。
情報連携がうまくいかないと、面接官が候補者の情報を十分に理解しないまま面接に臨んだり、合否判断が遅れて候補者が他社に流れてしまったりする事態が発生します。
採用担当に向いている人は、情報の整理と共有を効率的に行う仕組みを作ります。
たとえば、採用管理システム(ATS)を活用して候補者情報を一元管理したり、面接前に面接官へ候補者の経歴サマリーを送付したり、選考会議の資料を事前に準備して円滑な意思決定を支援したりします。
さらに、プロジェクト管理の視点も欠かせません。
採用活動全体を一つのプロジェクトとして捉え、タスクの洗い出し、優先順位付け、スケジュール管理、進捗管理を体系的に行う能力が求められます。
新卒採用のように長期間にわたるプロジェクトでは、特にこのスキルが重要になります。
説明会の開催、インターンシップの実施、選考の実施、内定者フォローなど、複数のタスクを並行して進めながら、全体のスケジュールを管理する必要があるのです。
優れたプロジェクト管理力を持つ採用担当者は、以下のような特徴があります。
- 採用活動全体のスケジュールを可視化している
- タスクの優先順位を明確にして効率的に進める
- 進捗状況を定期的にチェックし、遅れがあれば早期に対処する
- リスクを予測し、事前に対策を講じる
- 関係者に定期的に状況を報告し、協力を得る
また、社外との調整力も重要です。
人材紹介会社、求人広告会社、採用イベントの運営会社など、外部のパートナーとの円滑な連携が採用成功の鍵を握ります。
外部パートナーに対して自社の求める人材像や採用方針を明確に伝え、効果的なサポートを引き出すことができる人材が、採用担当として成果を上げます。
具体的な調整・管理業務の例を以下に示します。
- 月間の面接スケジュールを作成し、関係者に共有する
- 候補者ごとの選考進捗をトラッキングし、停滞があれば促進する
- 面接官向けの評価シートや質問項目を準備する
- 選考会議の日程調整と資料準備を行う
- 内定者フォローのイベントスケジュールを計画・実行する
- 採用予算の執行状況を管理し、必要に応じて調整する
このように、複雑な採用プロジェクトを円滑に進める調整力とプロジェクト管理力を持つ人材が、採用担当として向いているのです。
柔軟性と臨機応変さ(変化対応・オンライン選考等)
採用市場は常に変化しており、柔軟性と臨機応変さを持つ人材が採用担当として成功します。
近年の採用活動では、予測できない事態への対応が頻繁に求められるようになっています。
まず、市場環境の変化への対応力が重要です。
景気の変動、業界トレンドの変化、競合他社の採用戦略の変更など、外部環境は常に動いています。
たとえば、IT業界では慢性的な人材不足が続いており、従来の採用手法では十分な応募者を確保できない状況が生じています。
このような状況下で、採用担当に向いている人は固定観念にとらわれず、新しい採用手法にチャレンジする柔軟性を持っています。
ダイレクトリクルーティングやリファラル採用、副業人材の活用など、従来とは異なるアプローチを積極的に取り入れることができるのです。
次に、技術変化への適応力も欠かせません。
新型コロナウイルスの流行を契機に、オンライン選考が急速に普及しました。
ZoomやTeamsなどのツールを使った面接、録画面接、オンライン説明会など、デジタル技術を活用した採用手法が標準となっています。
採用担当に向いている人は、これらの新しいツールを積極的に学び、効果的に活用することができます。
オンライン面接ならではの注意点、たとえば通信環境の確認、背景の設定、カメラアングルの調整、画面共有の活用方法などを理解し、候補者にとって快適な選考体験を提供することができるのです。
また、個別対応の柔軟性も重要な要素です。
候補者一人ひとりの状況や要望は異なります。
在職中で平日の面接が難しい候補者には土曜日の面接を設定したり、遠方に住む候補者にはオンライン面接を提案したりと、それぞれの事情に合わせた柔軟な対応が求められます。
硬直的なルールに固執せず、候補者の立場に立って最適な解決策を見つけられる人材が、採用担当として活躍できます。
さらに、予期せぬトラブルへの対応力も試されます。
採用活動では様々なトラブルが発生する可能性があります。
面接官が急病で面接に来られなくなった、オンライン面接の通信トラブルが発生した、内定者が突然辞退を申し出てきたなど、想定外の事態に冷静に対処する能力が必要です。
臨機応変に対応できる採用担当者は、トラブルが発生しても慌てず、代替案を素早く考えて実行に移します。
面接官の代理を立てる、別の日時に面接を再設定する、候補者の不安を丁寧にヒアリングして解消策を提案するなど、状況に応じた最適な対応ができるのです。
柔軟性と臨機応変さが求められる具体的な場面を以下に示します。
- 応募が想定より少ない場合に、追加の採用手法を検討・実行する
- 優秀な候補者から条件面の相談があった際に、社内と調整して柔軟に対応する
- 選考途中で候補者の評価が変わった際に、選考フローを調整する
- 急な事業計画の変更で採用人数や求める人材像が変わった際に、速やかに方針を転換する
- 新しい採用ツールやサービスが登場した際に、積極的に試験導入する
また、学習意欲の高さも柔軟性の表れです。
採用市場のトレンド、法律の改正、新しい評価手法、効果的な面接テクニックなど、常に新しい知識を吸収し続ける姿勢が重要です。
セミナーへの参加、専門書の読書、他社の採用担当者との情報交換など、自己研鑽を続けられる人材が採用担当として成長していきます。
以下のような特徴を持つ人が、柔軟性と臨機応変さに優れているといえます。
- 「これまでのやり方」に固執せず、新しい方法を試す
- 状況の変化を素早く察知し、対応策を考える
- トラブルが起きても冷静に問題を整理し、解決策を実行する
- 候補者や関係者の多様なニーズに柔軟に応える
- 失敗を恐れず、チャレンジする姿勢を持つ
このように、変化の激しい採用市場において、柔軟に対応し臨機応変に行動できる人材が、採用担当として成果を上げることができるのです。
向いていない人の特徴と人選のコツ

向いていない人の傾向(意見を言えない・傾聴不足・受け身)
採用担当に向いている人の特徴を理解することと同じくらい、向いていない人の特徴を知ることも重要です。
適性のない人材を採用担当に配置してしまうと、採用活動の質が低下し、企業に大きな損失をもたらす可能性があります。
まず、意見を言えない人は採用担当には向いていません。
採用活動では、候補者の評価や採用方針について、自分の意見を明確に述べる場面が多くあります。
選考会議で「この候補者は○○の点で優れているため採用すべきだと考えます」といった具合に、根拠を持って自分の判断を伝えることが求められるのです。
しかし、意見を言えない人は、周囲の意見に流されたり、自分の評価に自信が持てなかったりします。
その結果、採用の意思決定が曖昧になり、優秀な人材を逃してしまうリスクが高まります。
また、経営層や現場の責任者から「どう思う?」と意見を求められた際に、「分かりません」「どちらでもいいです」といった曖昧な返答しかできないと、採用担当としての信頼を失ってしまいます。
次に、傾聴力が不足している人も採用担当には不向きです。
面接では候補者の話をじっくりと聞き、その人の本質を理解することが最も重要な任務です。
しかし、傾聴力が不足している人は、候補者が話している最中に話を遮ったり、自分の話ばかりしたり、表面的な情報しか引き出せなかったりします。
その結果、候補者の真の適性や可能性を見極められず、ミスマッチな採用につながるのです。
また、候補者からも「この面接官は自分の話を聞いてくれない」と感じられ、企業イメージの低下や辞退につながる可能性があります。
さらに、受け身の姿勢が強い人も採用担当には適していません。
採用活動は、指示を待つだけでは成果が上がらない仕事です。
市場の動向を自ら調査し、新しい採用手法を提案し、候補者に積極的にアプローチするなど、主体的に行動する姿勢が求められます。
受け身の人は、「言われたことはやるが、それ以上のことはしない」という姿勢になりがちです。
応募が少なくても改善策を考えない、選考が停滞していても放置する、新しい採用手法の情報収集をしないなど、積極性の欠如が採用活動の停滞を招くのです。
また、以下のような特徴を持つ人も採用担当には向いていません。
- 感情的になりやすい人:候補者から厳しい質問をされたり、内定辞退を告げられたりした際に、感情的に反応してしまうと、企業の印象を損ねます。常に冷静で客観的な対応が求められるため、感情のコントロールが苦手な人は不向きです。
- 細かい作業が苦手な人:採用活動では、応募者情報の管理、日程調整、書類の確認など、細かい事務作業が多く発生します。これらを雑に扱うと、ダブルブッキングや情報の漏洩などのトラブルにつながります。細部への注意力が欠けている人は向いていません。
- 人への興味が薄い人:採用担当の本質は「人」に関わる仕事です。候補者一人ひとりの背景や価値観に興味を持ち、その人の可能性を見出すことが求められます。人に対する興味や好奇心が薄い人は、この仕事にやりがいを感じにくく、成果も上がりにくいでしょう。
- プレッシャーに弱い人:採用活動では、「期限までに必要人数を確保しなければならない」というプレッシャーが常にあります。また、優秀な候補者を他社に取られるかもしれないという緊張感も伴います。このようなプレッシャーに耐えられない人は、採用担当として苦しむことになります。
向いていない人の具体的な行動パターンを以下に示します。
| 向いていない特徴 | 具体的な行動例 | 生じる問題 |
| 意見を言えない | 選考会議で発言しない | 意思決定が遅れる |
| 傾聴不足 | 候補者の話を遮る | ミスマッチな採用 |
| 受け身 | 指示待ちで改善提案をしない | 採用活動が停滞する |
| 感情的 | 内定辞退に感情的に反応 | 企業イメージの低下 |
これらの特徴を持つ人材を採用担当に配置すると、採用活動の質が低下し、優秀な人材を確保できないだけでなく、企業ブランドにも悪影響を及ぼす可能性があります。
人選の際には、これらの向いていない特徴に該当しないかを慎重に見極めることが重要です。
人選のポイント(ジャッジ型/フォロー型の見立て)
採用担当者を選ぶ際には、その人の資質やタイプを見極め、適材適所で配置することが重要です。
特に、採用担当には大きく分けて「ジャッジ型」と「フォロー型」という2つのタイプがあり、それぞれに適した役割があります。
まず、ジャッジ型の採用担当者について説明します。
ジャッジ型は、候補者の能力や適性を的確に見極め、合否を判断する能力に優れたタイプです。
このタイプの人材は、論理的思考力と客観性が高く、データや事実に基づいて冷静に判断を下すことができます。
面接では鋭い質問を投げかけて候補者の本質を見抜き、評価基準に照らして適切な判断を下します。
ジャッジ型が向いているのは、以下のような業務です。
- 書類選考での候補者のスクリーニング
- 面接での能力・適性の見極め
- 選考会議での評価のとりまとめと判断
- 採用基準の策定と評価方法の設計
- データ分析に基づく採用戦略の立案
ジャッジ型の人材は、採用の「質」を高める上で欠かせない存在です。
ただし、このタイプは候補者との関係構築や感情面でのフォローがやや苦手な傾向があるため、それを補完する体制が必要です。
一方、フォロー型の採用担当者は、候補者との信頼関係を築き、寄り添って支援することに長けたタイプです。
このタイプの人材は、高い共感力とコミュニケーション力を持ち、候補者の不安を解消したり、入社への意欲を高めたりすることが得意です。
面接では候補者がリラックスして話せる雰囲気を作り出し、企業の魅力を温かく伝えることができます。
フォロー型が向いているのは、以下のような業務です。
- 候補者との初期コンタクトと関係構築
- 会社説明会や面接での企業の魅力付け
- 内定者フォローと入社までのサポート
- 候補者からの質問や不安への丁寧な対応
- リファラル採用の推進と社員との連携
フォロー型の人材は、候補者の満足度を高め、内定承諾率や入社後の定着率を向上させることに貢献します。
ただし、このタイプは判断が情に流されやすい傾向があるため、客観的な評価基準を明確にする必要があります。
理想的には、ジャッジ型とフォロー型の両方の人材を採用チームに配置し、互いの強みを活かす体制を作ることです。
たとえば、以下のような役割分担が考えられます。
- ジャッジ型が書類選考と最終面接を担当し、フォロー型が一次面接と内定者フォローを担当する
- ジャッジ型が採用戦略と評価基準を設計し、フォロー型が候補者対応と関係構築を担当する
- 選考会議ではジャッジ型が客観的な評価を提示し、フォロー型が候補者の人柄や潜在能力を補足する
人選の際には、以下のポイントを確認すると良いでしょう。
ジャッジ型の適性を見極めるポイント:
- 論理的に物事を分析し、説明できるか
- データや事実に基づいて判断する習慣があるか
- 自分の意見を明確に述べることができるか
- 感情に流されず、客観的に評価できるか
- 複雑な情報を整理し、本質を見抜く力があるか
フォロー型の適性を見極めるポイント:
- 相手の話を丁寧に聞き、共感できるか
- 人との関係構築が得意で、信頼を得やすいか
- 相手の立場に立って考え、行動できるか
- 細やかな気配りとフォローができるか
- 人の可能性を信じ、応援する姿勢があるか
また、どちらのタイプにも共通して求められる基本的な資質があります。
それは、誠実さ、コミュニケーション能力の基礎、学習意欲、責任感、そして採用業務への興味や意欲です。
これらの基本的な資質を持った上で、ジャッジ型かフォロー型かという特性を見極めることが重要です。
人選の際には、以下のプロセスで進めることをおすすめします。
- 採用チームに必要な役割を明確にする(ジャッジ型とフォロー型の両方が必要か、どちらかで十分か)
- 候補者の過去の経験や実績から、どちらのタイプに近いかを判断する
- 面接や適性検査を通じて、具体的な資質や能力を確認する
- 試用期間を設けて実際の業務で適性を見極める
- 定期的にフィードバックを行い、強みを伸ばし弱みを補完する
このように、採用担当者のタイプを理解し、適材適所で配置することで、採用チーム全体のパフォーマンスを最大化することができるのです。
まとめ

採用担当に向いている人の特徴について、役割や適性、実務スキル、人選のコツまで詳しく解説してきました。
採用担当者には、高いコミュニケーション力、論理的思考力、調整力、柔軟性など、多様な能力が求められます。
特に重要なのは、候補者の話を傾聴し、企業の魅力を効果的に説明し、条件面で交渉できるコミュニケーション力です。
また、感覚ではなくデータに基づいて客観的に判断する論理的思考力も欠かせません。
実務面では、社内外の関係者と円滑に連携する調整力とプロジェクト管理力が成果に直結します。
さらに、変化の激しい採用市場において、新しい手法にチャレンジし、予期せぬ事態にも冷静に対処できる柔軟性と臨機応変さが求められます。
一方、意見を言えない、傾聴が不足している、受け身の姿勢が強いといった特徴を持つ人は、採用担当には向いていません。
人選の際には、ジャッジ型とフォロー型という2つのタイプを理解し、適材適所で配置することが重要です。
判断力に優れたジャッジ型と、関係構築が得意なフォロー型を組み合わせることで、採用チーム全体のパフォーマンスを最大化できます。
適切な採用担当者を配置することは、企業の未来を左右する重要な意思決定です。
本記事で紹介した特徴や適性を参考に、自社に最適な採用担当者を見極めてください。
そして、採用担当者が能力を最大限発揮できる環境を整え、継続的に成長をサポートすることで、優秀な人材の獲得と企業の発展につなげていきましょう。
採用活動にお困りの方は株式会社アクセスへご相談ください。
株式会社アクセスは、名古屋・愛知県内の求人専門の広告代理店として、これまでに累計10,261社以上の企業様の採用活動を支援してまいりました。
採用担当者の育成や選定に関するご相談はもちろん、効果的な求人媒体の選定から採用サイトの制作、採用動画の制作まで、採用活動のあらゆる場面でお客様をサポートいたします。
「採用担当者の配置に悩んでいる」「応募が集まらない」「採用活動の効率を上げたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
特に、Indeedをはじめとする求人媒体を活用した採用支援では、多くの成功事例を生み出しています。
採用のプロフェッショナルが、貴社の課題に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。
24時間求人掲載を受け付けており、いつでもお問い合わせいただけます。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-15-5592(受付時間 9:00〜18:00 土日祝日定休)までお電話いただくか、弊社ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。
採用成功事例やお役立ち情報も公開しておりますので、ぜひ弊社ウェブサイトもご覧ください。
貴社の採用活動を成功に導くため、株式会社アクセスが全力でサポートいたします。