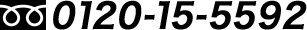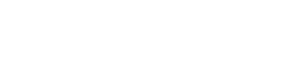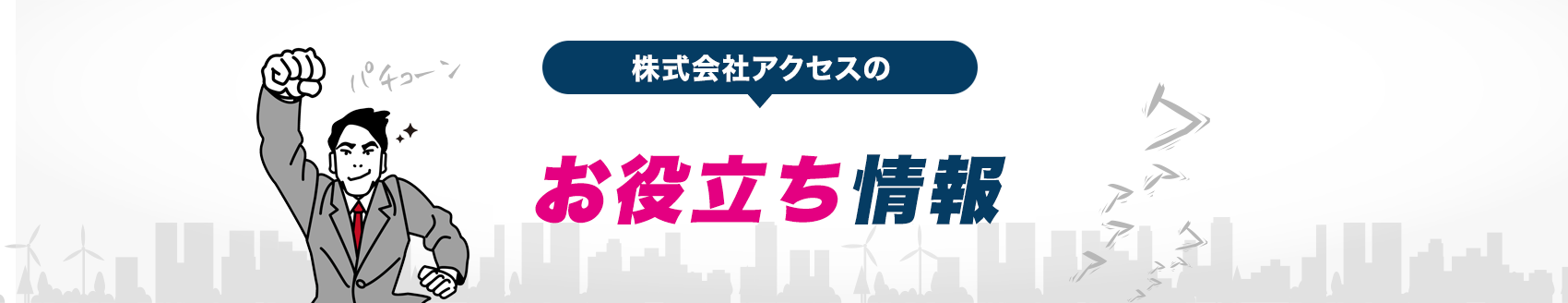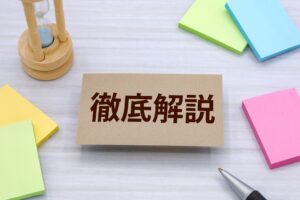採用コストを最適化!削減と指標の解説
企業の採用活動において、採用コストの増加は経営課題として無視できない問題となっています。
少子高齢化による労働人口の減少や、求職者の就職・転職に対する価値観の多様化により、優秀な人材を確保するための競争は年々激化しています。
その結果、求人広告費や人材紹介手数料などの外部コストはもちろん、採用担当者の人件費や選考にかかる時間といった内部コストも膨らみ続けているのが現状です。
しかし、やみくもにコストを削減すれば良いというわけではありません。
採用の質を落とさずに効率を高め、費用対効果を最大化することこそが、真の採用コスト最適化といえるでしょう。
本記事では、採用コストの基礎知識から具体的な削減策、さらには成功事例まで、人事・採用担当者が実践できる情報を網羅的に解説していきます。
採用活動の見直しを検討している方、採用単価を改善したい方は、ぜひ最後までお読みください。
CONTENTS
採用コストの基礎知識

採用コストとは何か?(内部コスト vs 外部コスト)
採用コストとは、企業が人材を採用するために支出する費用の総称を指します。
一見すると求人広告費や人材紹介会社への手数料だけを思い浮かべがちですが、実際にはもっと幅広い費用が含まれています。
採用コストは大きく分けて「外部コスト」と「内部コスト」の2つに分類されます。
外部コストは、社外の業者やサービスに支払う直接的な費用のことです。
具体的には以下のような項目が含まれます。
- 求人広告掲載費用(求人サイト、求人誌など)
- 人材紹介会社への成功報酬・手数料
- 合同企業説明会や就職フェアへの出展費用
- 採用パンフレットやリーフレットの制作費
- 採用サイトの制作・運用費用
- スカウトサービスの利用料金
- 適性検査やアセスメントツールの導入費用
これらの外部コストは金額が明確で把握しやすいため、多くの企業が採用コストとして認識している部分です。
一方、内部コストは社内で発生する間接的な費用であり、見落とされがちな重要な要素です。
内部コストには以下のような項目が該当します。
- 採用担当者の人件費(給与、社会保険料など)
- 面接官や現場社員の対応時間に相当する人件費
- 応募者との連絡・調整にかかる事務作業の工数
- 会社説明会や選考会場の設営・運営費用
- 応募者の交通費や宿泊費の負担
- リファラル採用の紹介報奨金
- 内定者フォローにかかる費用や時間
内部コストは金額として可視化されにくいため、採用コスト全体を把握する際に見落とされることが多いのです。
しかし、採用活動にかかる時間や労力を人件費に換算すると、実は外部コストと同等かそれ以上の金額になることも珍しくありません。
たとえば、採用担当者が1日8時間のうち5時間を採用業務に費やしている場合、その人件費の5/8が採用の内部コストとして計上されるべきです。
また、現場の管理職が面接対応に時間を割く場合も、その時間に相当する人件費が採用コストに含まれます。
このように、採用コストを正確に把握するためには、外部コストだけでなく内部コストもしっかりと計算に入れることが不可欠です。
両方のコストを合計することで、初めて採用活動の真のコストが見えてくるのです。
採用単価(1人あたりコスト)の計算方法と重要性
採用単価とは、1人の人材を採用するためにかかった平均コストのことで、採用活動の効率を測る最も重要な指標の一つです。
採用単価を算出することで、採用活動が適切に行われているか、コストパフォーマンスは良いかを客観的に評価できます。
採用単価の基本的な計算式は以下の通りです。
採用単価 = 総採用コスト ÷ 採用人数
たとえば、ある企業が年間で外部コスト500万円、内部コスト300万円の合計800万円を採用活動に投じ、10人の採用に成功した場合、採用単価は次のようになります。
800万円 ÷ 10人 = 80万円/人
この計算によって、1人を採用するために平均80万円のコストがかかっていることが分かります。
採用単価を把握する重要性は、主に以下の3点にあります。
第一に、採用活動の費用対効果を可視化できるという点です。
数字で明確に示されることで、経営層への報告や予算申請の際に説得力のある資料を作成できます。
第二に、年度ごとや採用手法ごとの比較が可能になるという点です。
前年度と比較して採用単価が上昇していれば、採用市場の競争激化や採用手法の見直しが必要なシグナルとなります。
逆に採用単価が下がっていれば、改善施策が効果を上げている証拠として評価できるでしょう。
第三に、採用チャネルごとの効率を比較できるという点です。
求人サイトA経由での採用単価が100万円、人材紹介会社B経由が150万円、リファラル採用が30万円といったように、チャネルごとに採用単価を算出することで、どの手法が最も効率的かを判断できます。
ただし、採用単価を計算する際にはいくつかの注意点があります。
まず、新卒採用と中途採用では採用プロセスやコスト構造が大きく異なるため、分けて計算するのが原則です。
新卒採用は一括採用で大量の応募者を処理するため、1人あたりの単価は比較的低くなる傾向があります。
一方、中途採用は個別対応が中心で、即戦力を求めるため人材紹介会社を利用するケースが多く、採用単価は高めになることが一般的です。
また、採用単価だけで判断せず、採用した人材の質や定着率も併せて評価することが重要です。
採用単価が低くても、早期離職率が高ければ、結果的に再度採用コストがかかり、トータルでは非効率になってしまいます。
さらに、採用単価は業界や職種によって大きく異なることも理解しておく必要があります。
IT業界やコンサルティング業界のように専門性が高く人材獲得競争が激しい業界では、採用単価が100万円を超えることも珍しくありません。
逆に、接客業や製造業の一般職では採用単価が数十万円程度に収まることもあります。
このように、採用単価は自社の採用活動を評価し、改善策を検討するための重要な指標です。
定期的に計算し、経年変化やチャネル別の違いを分析することで、より効率的な採用活動の実現につながります。
採用コストの相場・動向
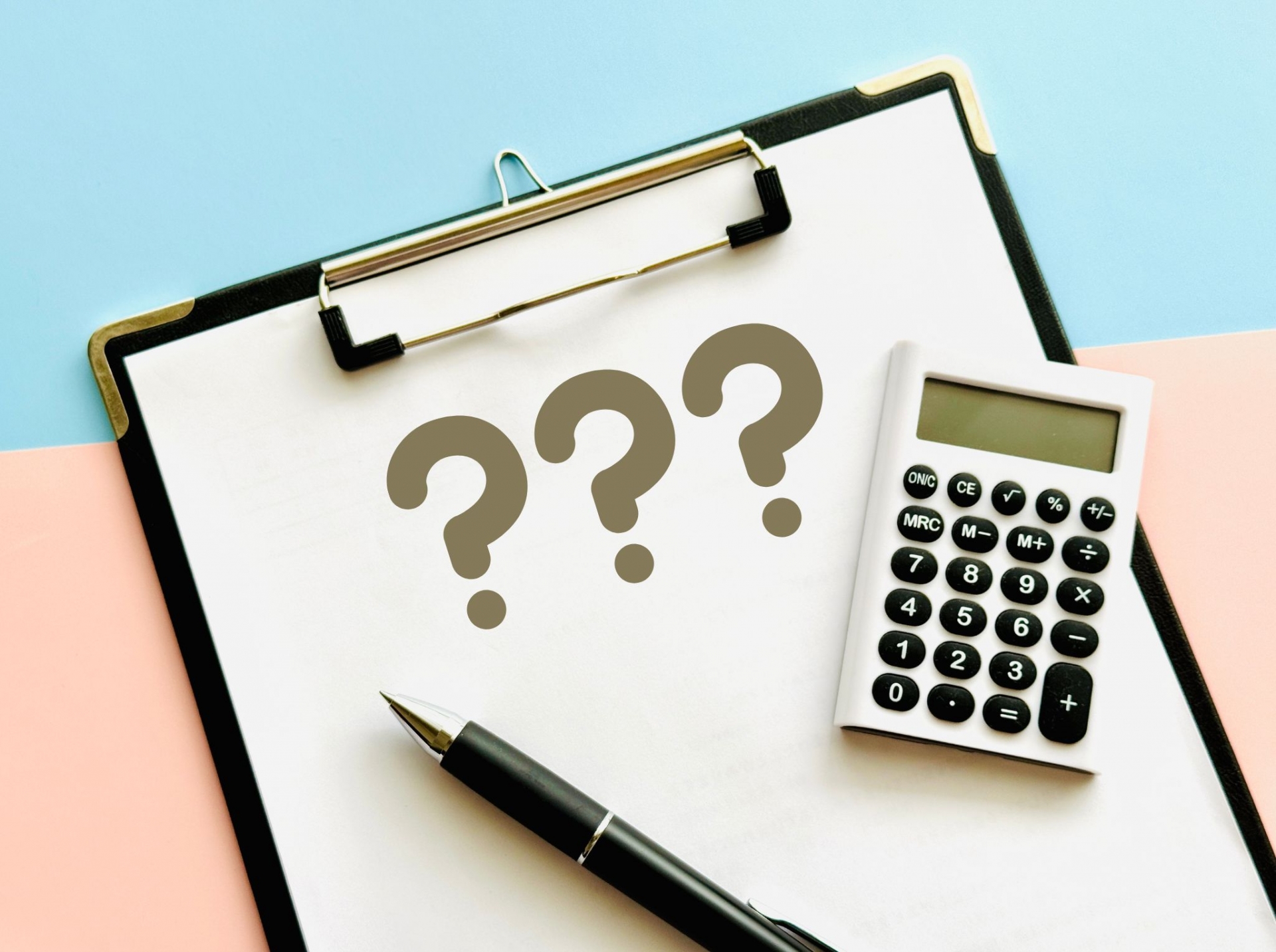
新卒・中途別の平均相場(過去実績から現状まで)
採用コストの相場は、新卒採用と中途採用で大きく異なります。
また、経済状況や労働市場の変化によって、年々その金額も変動しています。
ここでは、過去から現在に至るまでの採用コストの推移と、現在の平均相場について詳しく見ていきましょう。
まず、新卒採用の採用単価についてです。
株式会社リクルートの就職みらい研究所が発表している「就職白書」によると、2010年代前半の新卒採用単価は1人あたり40万円~50万円程度でした。
しかし、2015年頃から売り手市場が続き、企業間の採用競争が激化したことで、採用単価は徐々に上昇していきます。
2020年には新型コロナウイルスの影響で一時的に採用活動が停滞し、採用単価も若干下がる傾向が見られました。
しかし、2021年以降は再び採用市場が活性化し、2023年時点では新卒採用の平均単価は70万円~90万円程度になっているとされています。
企業規模や業界によってばらつきはありますが、新卒1人を採用するために100万円近いコストをかけている企業も増えているのが実態です。
新卒採用のコストが上昇している背景には、以下のような要因があります。
- 少子化による新卒人口の減少
- 学生の企業選択肢の多様化
- インターンシップや早期接触への投資増加
- オンライン選考システムの導入コスト
- 採用広報や採用ブランディングへの注力
特に、インターンシップは採用活動の入り口として重要性が増しており、その実施コストも採用単価を押し上げる要因となっています。
一方、中途採用の採用単価は新卒採用よりも高額になる傾向があります。
中途採用では、人材紹介会社(エージェント)を利用するケースが多く、成功報酬として理論年収の30%~35%程度を手数料として支払うのが一般的です。
たとえば、年収500万円の人材を採用した場合、人材紹介会社への手数料は150万円~175万円となります。
これに社内の選考コストや求人広告費を加えると、中途採用の採用単価は100万円~200万円程度が相場といえるでしょう。
特に、専門性の高いIT人材や管理職クラスの採用では、採用単価が300万円を超えることも珍しくありません。
中途採用のコストが高い理由には、以下のような背景があります。
- 即戦力を求めるため、条件に合う人材が限られる
- 転職潜在層へのアプローチにコストがかかる
- 人材紹介会社への依存度が高い
- 個別対応が必要で効率化しにくい
- スキルマッチの精度を上げるための選考プロセスが複雑
また、近年ではダイレクトリクルーティングやリファラル採用など、新しい採用手法も普及してきています。
ダイレクトリクルーティングは、企業側から候補者に直接アプローチする手法で、スカウトサービスの利用料として月額数十万円程度のコストがかかります。
しかし、人材紹介会社を経由しないため、成功報酬が発生せず、トータルでの採用単価を抑えられる可能性があります。
リファラル採用は、社員の紹介によって人材を採用する手法で、紹介者への報奨金として5万円~30万円程度を支払うのが一般的です。
採用単価を大幅に抑えられるだけでなく、定着率も高いことから、多くの企業が注力している採用手法です。
過去から現在までの採用コストの推移を見ると、全体的に上昇傾向にあることが分かります。
しかし、採用手法の多様化によって、企業は自社に合った効率的な採用戦略を選択できる時代になってきているともいえるでしょう。
業界別・企業規模別の差異と最新傾向
採用コストは、業界や企業規模によって大きく異なります。
それぞれの特性や採用市場の状況を理解することで、自社の採用コストが適正かどうかを判断する基準を持つことができます。
まず、業界別の採用コストについて見ていきましょう。
IT・通信業界は、最も採用コストが高い業界の一つとして知られています。
エンジニアやデザイナーなど専門職の需要が供給を大きく上回っており、優秀な人材の獲得競争は熾烈を極めています。
中途採用では、採用単価が150万円~300万円に達することも珍しくありません。
特に、AIやデータサイエンス、セキュリティといった先端分野の人材は希少性が高く、年収の50%以上を採用コストとして投じるケースもあるのが実情です。
金融業界も採用コストが高い傾向にあります。
コンプライアンスやリスク管理が重視されるため、選考プロセスが慎重かつ複雑になり、選考期間が長期化することで内部コストが膨らみやすいという特徴があります。
また、高度な専門知識や資格が求められることも、採用単価を押し上げる要因となっています。
コンサルティング業界や広告業界も、高いスキルと経験を持つ人材を求めるため、採用単価は高めになる傾向があります。
特に、クリエイティブ職や戦略コンサルタントなど、希少性の高いポジションでは採用コストが200万円を超えることもあります。
一方、製造業や小売業、飲食業などは、比較的採用単価が低めに抑えられる業界です。
特に現場スタッフやオペレーション職の採用では、求人サイトや地域密着型の採用手法が効果的で、採用単価は30万円~60万円程度に収まることが多いでしょう。
ただし、製造業でも研究開発職やエンジニア職の採用では、他業界と同様に高額な採用コストが発生することがあります。
次に、企業規模別の採用コストについて考えてみましょう。
大企業は、採用人数が多いためスケールメリットを活かせるという利点があります。
たとえば、新卒採用で100人規模の採用を行う場合、1回の合同説明会や会社説明会で多数の学生にアプローチできるため、1人あたりの採用単価は比較的低く抑えられます。
また、自社の採用サイトや採用ブランドが確立されているため、応募者が自然に集まりやすく、外部コストを抑えられる傾向があります。
ただし、大企業でも採用担当者の人数が多く、選考プロセスが複雑になることで、内部コストが膨らみやすいという側面もあります。
中小企業は、採用人数が少ないためスケールメリットを得にくく、1人あたりの採用単価が高くなりがちです。
特に、知名度が低い企業では、求人広告を出しても応募が集まりにくく、人材紹介会社に頼らざるを得ないケースが多くなります。
その結果、外部コストの比率が高くなり、採用単価が100万円を超えることも珍しくありません。
しかし、中小企業には独自の強みもあります。
社長や役員が直接採用活動に関わることで、企業のビジョンや魅力を直接伝えられるという利点があります。
また、採用プロセスがシンプルで意思決定が早いため、優秀な候補者を逃さず採用できる可能性が高いという側面もあります。
最近の傾向としては、企業規模に関わらず、採用手法の多様化が進んでいる点が挙げられます。
従来の求人広告や人材紹介会社だけでなく、以下のような手法が注目されています。
- SNSを活用した採用広報
- ダイレクトリクルーティング(スカウト型採用)
- リファラル採用(社員紹介制度)
- アルムナイ採用(退職者の再雇用)
- 副業・フリーランス人材の活用
特に、ダイレクトリクルーティングは中小企業でも導入が進んでおり、人材紹介会社への依存度を下げることで採用コストの削減に成功する事例が増えています。
また、リファラル採用は業界や企業規模を問わず効果的とされており、採用単価を大幅に抑えられるだけでなく、採用後の定着率も高いというメリットがあります。
業界別・企業規模別の採用コストの差異を理解することで、自社の採用戦略を客観的に評価し、改善の方向性を見出すことができるでしょう。
採用コストを削減する具体策

採用チャネル・媒体を見直す
採用コストを削減する上で、最も効果的なアプローチの一つが採用チャネルと媒体の見直しです。
どの採用手法を選ぶかによって、コストだけでなく採用の質や効率も大きく変わってきます。
まず重要なのは、現在利用している採用チャネルごとの効果を定量的に分析することです。
各チャネルから何人の応募があり、何人が選考に進み、最終的に何人を採用できたのか、そして採用単価はいくらだったのかを明確にしましょう。
この分析によって、費用対効果の低いチャネルと高いチャネルが浮き彫りになります。
求人サイトの見直しは、多くの企業がまず取り組むべき課題です。
複数の求人サイトに同時掲載している場合、それぞれのサイトからの応募数と採用実績を比較してみてください。
応募は多くても採用に至らないサイトは、ターゲット層とのミスマッチが起きている可能性があります。
逆に、応募数は少なくても採用率が高いサイトは、質の高い候補者が集まっている証拠といえるでしょう。
求人サイトを選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 自社の求める人材層が利用しているか
- 業界や職種に特化したサイトか総合サイトか
- 掲載料金と期間のバランスは適切か
- スカウト機能など追加サービスの有用性
- 応募管理や候補者とのやり取りのしやすさ
必ずしも大手総合求人サイトが最適とは限りません。
職種や業界に特化したニッチな求人サイトの方が、採用単価を抑えつつ、質の高い採用ができるケースも多くあります。
人材紹介会社の活用方法も見直しが必要です。
人材紹介会社は成功報酬型で採用単価が高額になりますが、採用難易度の高いポジションに限定して利用するというメリハリをつけることが重要です。
また、複数の人材紹介会社と取引がある場合は、各社の成功率や候補者の質を評価し、パフォーマンスの高い会社に絞り込むことも検討しましょう。
さらに、人材紹介会社との料金交渉も有効な手段です。
年間の採用予定数が多い場合や、継続的な取引関係がある場合は、成功報酬率を引き下げる交渉の余地があります。
通常30%~35%の手数料を25%~28%に下げられれば、大きなコスト削減につながります。
近年注目されているのが、**ダイレクトリクルーティング(スカウト型採用)**です。
企業側から候補者に直接アプローチする手法で、人材紹介会社を介さないため成功報酬が発生しません。
主なダイレクトリクルーティングサービスには、以下のようなものがあります。
| サービスタイプ | 特徴 | 適している企業 |
| データベース型 | 登録者のデータベースから検索してスカウト | 採用担当者のリソースがある企業 |
| AI マッチング型 | AIが最適な候補者を提案 | 効率的にアプローチしたい企業 |
| SNS型 | LinkedIn などのSNSを活用 | グローバル人材を採用したい企業 |
ダイレクトリクルーティングは、初期費用や月額費用はかかるものの、成功報酬がないため、複数人採用する場合はトータルコストを抑えられるメリットがあります。
ただし、候補者へのスカウトメッセージ作成や日程調整などの工数がかかるため、社内リソースとのバランスを考慮して導入を検討する必要があります。
**リファラル採用(社員紹介制度)**も、コスト削減に非常に効果的な手法です。
社員が知人や友人を紹介し、採用に至った場合に紹介者へ報奨金を支払う仕組みですが、この報奨金は通常5万円~30万円程度で、人材紹介会社の手数料と比べて圧倒的に低コストです。
リファラル採用を成功させるポイントは以下の通りです。
- 社員が紹介しやすい仕組みづくり(専用フォームなど)
- 紹介のインセンティブ設定(報奨金の魅力化)
- 定期的なリファラル促進キャンペーンの実施
- 紹介プロセスの透明化と進捗共有
- 社内広報による積極的な周知
リファラル採用は、入社後の定着率が高く、企業文化にマッチしやすいという副次的なメリットもあります。
自社採用サイトの強化も、中長期的なコスト削減につながります。
求人サイトに頼らず、自社サイトから直接応募を獲得できれば、媒体費用を大幅に削減できるだけでなく、企業の魅力をより深く伝えることができます。
自社採用サイトを強化する際のポイントは以下の通りです。
- SEO対策で検索エンジンからの流入を増やす
- 社員インタビューや働き方の紹介で魅力を伝える
- 応募プロセスをシンプルにして離脱を防ぐ
- スマートフォン対応を徹底する
- 採用情報をこまめに更新する
また、SNSを活用した採用広報も注目されています。
X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LinkedIn などを通じて、企業の日常や社員の活躍を発信することで、潜在的な求職者との接点を増やすことができます。
SNS採用のメリットは、基本的に無料で情報発信ができることと、拡散によって認知度を高められることです。
ただし、継続的な運用が必要で、コンテンツ作成に工数がかかる点は考慮が必要です。
このように、採用チャネルと媒体を戦略的に見直すことで、コストを削減しながらも採用の質を維持・向上させることが可能です。
自社の採用状況を定期的に分析し、最適なチャネルミックスを追求していきましょう。
選考プロセスと効率化の改善
採用コストの中でも見落とされがちなのが、選考プロセスにかかる内部コストです。
選考期間が長引けば、その分だけ採用担当者や面接官の工数が増え、コストが膨らんでいきます。
また、選考期間の長期化は優秀な候補者を他社に取られるリスクも高めるため、スピードと効率の両立が重要です。
まず取り組むべきは、選考フローの見直しと簡素化です。
多くの企業では、書類選考、一次面接、二次面接、最終面接といった複数段階の選考を行っていますが、本当にすべてのステップが必要かを検証してみましょう。
たとえば、以下のような見直しが考えられます。
- 書類選考の基準を明確化し、判断時間を短縮する
- 一次面接と二次面接を統合する
- Web面接を活用して日程調整の柔軟性を高める
- 最終面接の判断基準を事前に明確にする
選考フローを1段階減らすだけでも、候補者の拘束時間が短くなり、辞退率の低下につながるだけでなく、社内の工数削減にも直結します。
書類選考の効率化も重要なポイントです。
応募者が多い場合、書類選考だけで膨大な時間を費やしてしまうことがあります。
効率化の方法としては以下が挙げられます。
- 応募時の必須項目を最適化し、判断材料を絞る
- 職務経歴書のフォーマットを指定して比較しやすくする
- 合否判断の基準を明文化し、複数人でチェックする体制を減らす
- AI やATS(採用管理システム)を活用してスクリーニングを自動化する
特に、ATS の導入は中長期的に大きな効率化につながります。
応募者情報の一元管理、選考状況の可視化、自動返信メールの設定などにより、採用担当者の事務作業を大幅に削減できるのです。
面接の効率化も重要な課題です。
面接は採用プロセスの中で最も時間とコストがかかる部分ですが、工夫次第で効率を高められます。
面接効率化のポイントは以下の通りです。
- 面接の目的と評価項目を事前に明確にする
- 構造化面接を導入し、質問内容を標準化する
- 面接時間を30分~45分に設定し、時間厳守を徹底する
- Web面接を積極的に活用する
- 複数候補者を同日に集中して面接する
特に、構造化面接は面接の質を高めながら時間短縮も実現できる優れた手法です。
事前に質問項目と評価基準を設定しておくことで、面接官による評価のばらつきを減らし、より公平で正確な判断ができるようになります。
また、Web面接の活用は、コロナ禍をきっかけに急速に普及しました。
Web面接のメリットは以下の通りです。
- 会場設営や移動時間が不要になる
- 遠方の候補者とも気軽に面接できる
- 日程調整の柔軟性が高まる
- 面接の録画・記録が可能で振り返りやすい
- 採用担当者の負担軽減につながる
ただし、Web面接では候補者の雰囲気や企業の魅力が伝わりにくいという側面もあるため、一次面接はWeb、最終面接は対面といった使い分けも有効です。
選考期間の短縮も、優秀な人材を確保する上で重要な要素です。
応募から内定までの期間が長いと、候補者は他社に流れてしまう可能性が高まります。
選考期間を短縮するための施策には、以下のようなものがあります。
- 面接の日程調整を迅速に行う(24時間以内の返信を目標に)
- 面接官のスケジュール確保を優先する
- 合否判断の会議を週1回など定期開催にする
- 意思決定プロセスをシンプルにする
- 候補者とのコミュニケーションを密にして不安を解消する
理想的には、応募から内定まで2週間~1ヶ月以内に完結させることを目標にすべきでしょう。
内定者フォローの効率化も見落とせません。
せっかく内定を出しても、入社までの期間に辞退されてしまっては、それまでの採用コストが無駄になってしまいます。
内定者フォローを効率的に行うポイントは以下の通りです。
- 内定者専用のコミュニケーションツールを用意する
- 定期的な情報提供や交流会を企画する
- 先輩社員との面談機会を設ける
- 入社前研修をオンライン化して参加しやすくする
- 不安や疑問にはすぐに対応する体制を整える
内定者フォローを仕組み化することで、採用担当者の負担を減らしながら、内定辞退率を低下させることができます。
最後に、採用データの活用も効率化には欠かせません。
各選考段階での通過率、面接官ごとの評価傾向、採用チャネルごとの採用率など、データを蓄積・分析することで、改善すべきポイントが明確になります。
たとえば、一次面接の通過率が極端に低い場合は、書類選考の基準が甘すぎる可能性があります。
逆に最終面接での辞退率が高い場合は、給与条件や企業の魅力が十分に伝わっていないのかもしれません。
このように、データに基づいた改善サイクルを回すことで、継続的に選考プロセスを最適化していくことが可能です。
選考プロセスの効率化は、単なるコスト削減だけでなく、候補者体験の向上や採用の質向上にもつながる重要な取り組みです。
注意点・成功事例から学ぶ戦略
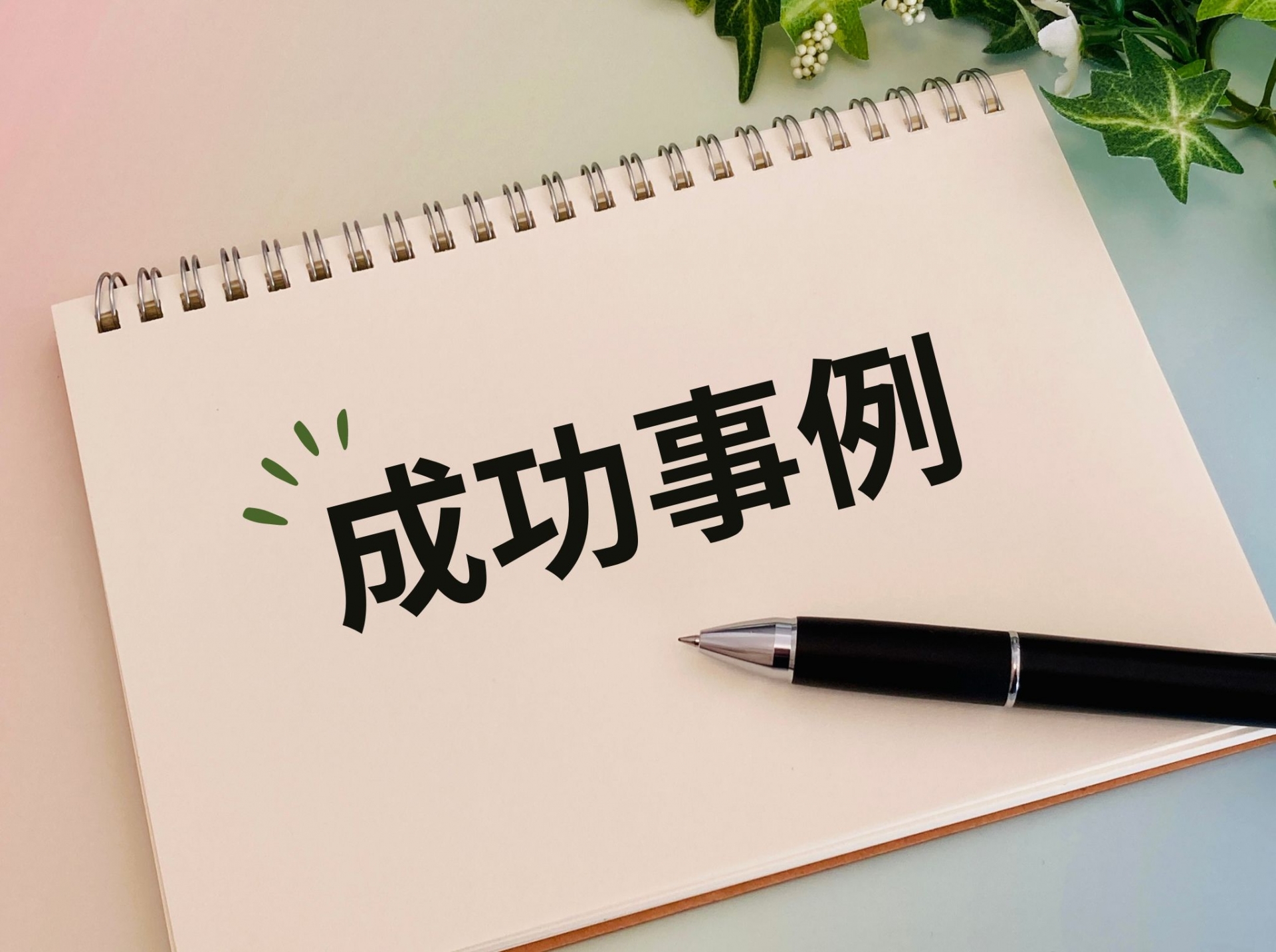
コスト削減時に失敗しやすい落とし穴
採用コストの削減に取り組む際、やみくもにコストを削ると、かえって採用の質が低下し、長期的には損失を招くリスクがあります。
ここでは、採用コスト削減時によくある失敗パターンと、その回避方法について解説します。
最も多い失敗は、採用の質を犠牲にしてコスト削減を優先してしまうことです。
たとえば、求人広告費を削減するために安価な媒体のみに絞った結果、応募者の質が大幅に低下し、結局採用に至らなかったというケースがあります。
また、人材紹介会社の利用を完全にやめてしまい、採用難易度の高いポジションで全く採用できなくなるという事態も起こり得ます。
コスト削減は重要ですが、採用の成功率や人材の質を維持することが大前提です。
削減できる部分とできない部分を見極め、メリハリをつけることが重要です。
次に多い失敗が、短期的な視点でコスト削減を行い、長期的なコスト増を招くパターンです。
典型的な例は、選考プロセスを過度に簡略化して、入社後のミスマッチが増えることです。
十分な見極めができないまま採用すると、早期離職につながり、再度採用コストがかかるだけでなく、教育コストも無駄になってしまいます。
また、内定者フォローを削減した結果、内定辞退率が上昇し、追加採用が必要になるケースもあります。
採用コストは単年度だけでなく、採用後の定着率や活躍度も含めて評価する必要があります。
三つ目の落とし穴は、採用担当者への負担が過大になることです。
外部コストを削減するために、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用を導入するのは良いことですが、それには社内の工数がかかります。
候補者へのスカウトメッセージ作成、社員への紹介依頼、選考日程の調整など、採用担当者の業務量が増えすぎると、本来の戦略的な採用活動に時間を割けなくなるリスクがあります。
コスト削減策を導入する際は、社内リソースとのバランスを考慮し、必要に応じて業務の優先順位を見直すことが重要です。
四つ目の失敗例は、採用ブランディングへの投資を削減してしまうことです。
短期的には求人広告費や採用イベントへの出展費を削減できますが、企業の認知度や魅力が低下すると、中長期的に応募者数の減少や採用難易度の上昇を招く可能性があります。
特に、新卒採用では企業のブランドイメージが応募意欲に大きく影響するため、採用広報や学生との接点づくりへの投資は継続的に行うべき領域といえます。
五つ目の注意点は、データに基づかない意思決定です。
「この採用チャネルは効果がなさそうだから削減しよう」という感覚的な判断ではなく、実際のデータを分析して効果を検証することが不可欠です。
応募数は少なくても採用率が高いチャネルを削減してしまうと、結果的に採用単価が上昇する可能性があります。
各採用チャネルの費用対効果を定量的に評価し、データに基づいた意思決定を行いましょう。
六つ目の落とし穴は、社内の協力体制が不十分なまま進めることです。
採用コスト削減には、採用担当者だけでなく、現場の管理職や経営層の理解と協力が必要です。
たとえば、リファラル採用を推進するには、社員全員の協力が不可欠ですし、選考期間の短縮には面接官のスケジュール確保が必要です。
社内への説明と協力依頼を丁寧に行い、全社的な取り組みとして進めることが成功の鍵となります。
最後に、法令遵守を軽視するリスクも注意が必要です。
コスト削減のために選考プロセスを簡略化しすぎると、適切な審査が行われず、後々トラブルになる可能性があります。
また、求人広告の記載内容や面接での質問事項など、労働関連法規を遵守することは最低限の前提条件です。
コンプライアンスを守りながら、効率的な採用活動を実現しましょう。
これらの落とし穴を避けるためには、以下の原則を守ることが重要です。
- 採用の質を最優先に考える
- 短期的なコスト削減だけでなく、長期的な視点を持つ
- データに基づいた意思決定を行う
- 社内リソースとのバランスを考慮する
- 全社的な協力体制を構築する
- 法令遵守を徹底する
採用コストの削減は目的ではなく、優れた人材を効率的に採用するための手段であることを忘れずに、バランスの取れた戦略を実行していきましょう。
成功事例から学ぶ削減モデル
採用コスト削減に成功している企業の事例を学ぶことで、自社に適用できる具体的なヒントを得ることができます。
ここでは、業界や企業規模の異なる複数の成功事例を紹介し、そこから導き出される成功の共通パターンを解説します。
事例1:IT企業A社のダイレクトリクルーティング活用
A社は、従業員300人規模のIT企業で、エンジニアの採用に年間3,000万円以上のコストをかけていました。
人材紹介会社への依存度が高く、1人あたりの採用単価が200万円を超える状況でした。
そこで、A社はダイレクトリクルーティングサービスを導入し、自社で候補者にアプローチする体制を整えました。
最初の半年間は採用担当者がスカウトメッセージの作成や候補者との関係構築に苦戦しましたが、PDCAサイクルを回してノウハウを蓄積していきました。
具体的には以下の取り組みを行いました。
- エンジニアメンバーにも協力を依頼し、技術的な魅力を伝える
- スカウトメッセージのテンプレートを複数パターン用意して効果測定
- 返信率の高い候補者の特徴を分析して対象を絞り込む
- カジュアル面談を積極的に実施して候補者との関係を構築
その結果、導入から1年後には年間10人のエンジニア採用のうち6人をダイレクトリクルーティング経由で獲得し、採用単価を平均80万円まで削減することに成功しました。
年間の採用コストは3,000万円から1,500万円に半減し、1,500万円のコスト削減を実現したのです。
A社の成功要因は、短期的な成果を求めず、中長期的な視点で採用力を高めた点にあります。
事例2:製造業B社のリファラル採用強化
B社は、従業員500人規模の製造業で、生産現場の技術職の採用に課題を抱えていました。
地方に拠点があるため応募者が集まりにくく、人材紹介会社に頼ると1人あたり150万円近いコストがかかっていました。
そこで、B社はリファラル採用制度を本格的に導入し、社員が友人や知人を紹介しやすい環境を整えました。
具体的な施策は以下の通りです。
- 紹介報奨金を1人あたり20万円に設定(採用成立時に支給)
- 社内報やメールで定期的にリファラル採用を周知
- 紹介プロセスを簡素化し、専用フォームで気軽に応募できるように
- 紹介された候補者には選考過程を丁寧にフォロー
- 紹介者にも選考状況を随時共有して不安を解消
導入から2年間で、年間20人の採用のうち12人がリファラル経由となり、採用単価は平均40万円まで低下しました。
さらに、**リファラル採用で入社した社員の3年後定着率は95%**と、他の採用チャネルと比較して圧倒的に高い結果となりました。
B社の成功の鍵は、社員が紹介しやすい仕組みを徹底的に整えた点と、紹介者・候補者双方へのきめ細かいフォローにあります。
事例3:小売業C社の自社採用サイト強化
C社は、全国に50店舗を展開する小売企業で、店舗スタッフの採用に毎年2,000万円以上を費やしていました。
求人サイトへの掲載費用が大きな負担となっており、応募単価も1件あたり2万円を超える状況でした。
そこで、C社は自社採用サイトのリニューアルに100万円を投資し、以下の改善を行いました。
- 先輩社員のインタビュー動画を20本以上掲載
- 店舗ごとの雰囲気や働き方を詳細に紹介
- 応募フォームをスマホ対応にして入力項目を最小限に
- SEO対策を徹底し、地域名×職種名で検索上位を獲得
- SNS(Instagram、X)と連動して情報発信
リニューアルから1年後、自社サイト経由の応募数は月間10件から50件に増加し、採用サイトからの直接応募が全体の40%を占めるようになりました。
求人サイトへの依存度が下がり、年間の採用コストは2,000万円から1,200万円に削減されました。
C社の成功ポイントは、初期投資を惜しまず、候補者に魅力が伝わるコンテンツを充実させたことです。
事例4:ベンチャー企業D社の選考プロセス効率化
D社は、従業員100人規模のベンチャー企業で、急成長に伴い年間30人以上の採用が必要でした。
しかし、採用担当者が2人しかおらず、選考プロセスが煩雑で工数がかかりすぎるという課題を抱えていました。
そこで、D社は選考フローを根本的に見直し、以下の改革を実施しました。
- 選考段階を4段階から2段階(一次面接+最終面接のみ)に削減
- 一次面接は30分のWeb面接に統一し、全採用ポジション共通の質問項目を設定
- 書類選考の基準を明文化し、合否判断を迅速化
- ATS(採用管理システム)を導入して応募者管理を自動化
- 最終面接は代表と現場責任者が同時に行い、1回で判断
これにより、応募から内定までの期間が平均45日から18日に短縮され、候補者の辞退率も大幅に低下しました。
採用担当者の業務時間も30%削減され、戦略的な採用活動に時間を割けるようになりました。
D社の成功要因は、スピード重視の選考プロセスを構築し、意思決定を迅速化した点にあります。
これらの成功事例から導き出される共通の成功パターンは以下の通りです。
- 自社の課題を明確に特定する
- 一つの施策に集中して取り組む
- 短期的な成果を求めず、継続的に改善する
- データを活用してPDCAサイクルを回す
- 社内の協力体制を構築する
- 候補者体験を重視する
また、成功企業に共通するのは、コスト削減だけでなく、採用の質や効率も同時に向上させている点です。
単に費用を削るのではなく、より効果的な採用手法に投資をシフトすることで、結果的にコスト削減と採用力強化の両立を実現しています。
これらの事例を参考に、自社の状況に合った採用コスト削減策を検討してみてください。
まとめ

採用コストの最適化は、企業の持続的な成長を支える重要な経営課題です。
本記事では、採用コストの基礎知識から具体的な削減策、注意点、成功事例まで幅広く解説してきました。
採用コストは外部コストと内部コストの両方を正確に把握することが第一歩であり、採用単価を定期的に計算して自社の採用活動を評価することが重要です。
コスト削減には、採用チャネルの見直しや選考プロセスの効率化が効果的ですが、採用の質を犠牲にしないよう注意が必要です。
成功事例から学べるのは、一つの施策に集中して継続的に改善し、データに基づいてPDCAサイクルを回すことの重要性です。
採用コストを抑えながらも優秀な人材を獲得するためには、自社に合った採用手法を見つけ、戦略的に採用活動を進めることが求められます。
適切なコストで質の高い人材を採用することが、企業の未来を創ることを忘れずに、効果的な採用活動を実践していきましょう。
採用活動にお困りの方は株式会社アクセスへご相談ください。
株式会社アクセスは、名古屋・愛知県内の求人専門の広告代理店として、これまでに累計10,261社以上の企業様の採用活動を支援してまいりました。
採用コストの削減はもちろん、効果的な求人媒体の選定から採用サイトの制作、採用動画の制作まで、採用活動のあらゆる場面でお客様をサポートいたします。
特に、Indeedをはじめとする求人媒体を活用した採用支援では、多くの成功事例を生み出しています。
「採用コストを削減したい」「応募が集まらない」「採用活動の効率を上げたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
24時間求人掲載を受け付けており、採用のプロフェッショナルが貴社の課題に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-15-5592(受付時間 9:00〜18:00 土日祝日定休)までお電話いただくか、弊社ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。
採用成功事例やお役立ち情報も公開しておりますので、ぜひ弊社ウェブサイトもご覧ください。
貴社の採用活動を成功に導くため、株式会社アクセスが全力でサポートいたします。