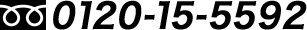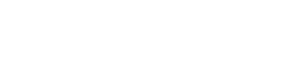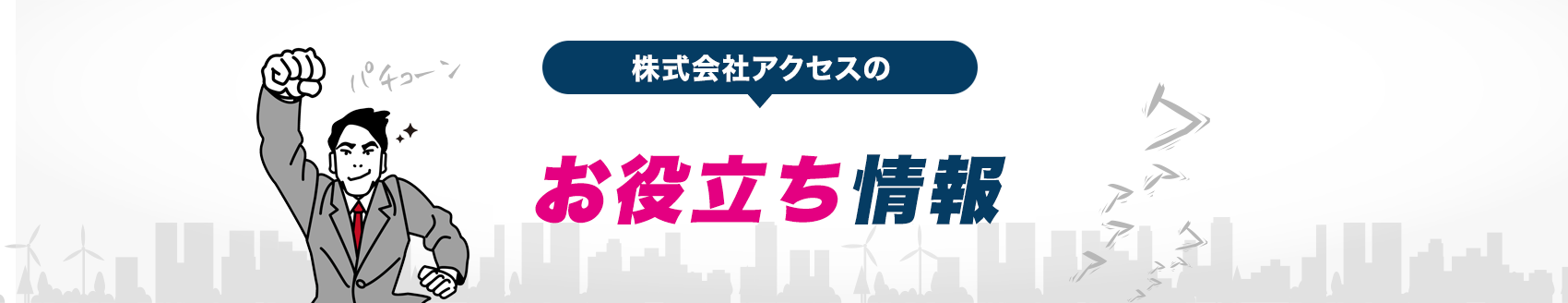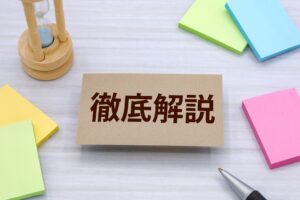中途採用の最適時期と勝ち筋
中途採用を成功させるには、いつ求人を出すかというタイミングが極めて重要です。
優秀な人材を獲得したいと考えていても、求職者の動きが少ない時期に募集しても応募は集まりません。
逆に、多くの企業が採用活動を活発化させる時期には、競合との激しい人材獲得競争に巻き込まれるリスクがあります。
中途採用市場には明確な繁閑の波があり、求職者が動く時期と企業が採用を強化する時期には一定のパターンが存在します。
このパターンを理解し、自社の採用計画に合わせた最適なタイミングで募集をかけることが、採用成功の鍵を握るのです。
しかし、多くの採用担当者が「いつ求人を出せば良いのか分からない」「応募が集まらず困っている」「採用スケジュールの立て方が分からない」といった悩みを抱えています。
本記事では、中途採用市場において求職者と企業が動く時期の全体像を明らかにし、繁忙期と閑散期それぞれに適した募集戦略を詳しく解説します。
さらに、入社時期から逆算した実践的なスケジュールの立て方まで、採用担当者がすぐに実務で活用できる情報をお届けします。
中途採用の最適時期を知り、戦略的に採用活動を進めることで、限られた予算と時間の中で最大限の成果を上げることができます。
ぜひ最後までお読みいただき、自社の採用活動に役立ててください。
CONTENTS
中途採用が動く時期の全体像

求職者が増える月(1〜3月・6〜7月・9〜11月)
中途採用市場では、求職者の動きが活発になる時期が年に3回あります。
この時期を理解することで、応募が集まりやすいタイミングを見極めることができます。
まず、最も求職者が動くのは1月から3月です。
この時期は、多くの会社員が冬のボーナスを受け取った後であり、転職を決意して動き出す人が最も多くなります。
特に、3月末の年度末に退職し、4月から新しい会社でスタートを切りたいと考える求職者が多いため、1月から2月にかけて転職活動が最も活発化します。
企業側も新年度に向けて組織体制を整えたいという思惑があるため、求職者と企業のニーズが一致する時期といえます。
この時期の求職者の特徴は以下の通りです。
- ボーナスを受け取ってから退職する計画的な転職者が多い
- 年度の区切りで転職したいという意識が強い
- 転職への本気度が高く、スピード感を持って活動している
- 競合他社も積極的に採用活動を行うため、優秀な人材の奪い合いになる
次に動きが活発になるのが、6月から7月の夏のボーナス後です。
春の繁忙期ほどではありませんが、夏のボーナスを受け取ってから転職活動を始める求職者が一定数存在します。
特に、上半期の評価や人事異動の結果に不満を持った人材が動き出す傾向があります。
この時期は、春の採用活動で人材を確保できなかった企業が再度募集をかけることも多く、需給バランスが取れやすい時期です。
夏の転職市場の特徴は以下の通りです。
- 上半期の評価や配置転換をきっかけに転職を考える人が多い
- 7月入社または9月・10月入社を目指して活動する
- 春ほど競争が激しくないため、じっくり候補者と向き合える
- 新卒採用が落ち着いた企業が中途採用にリソースを割ける時期
そして、9月から11月も求職者が動く時期として知られています。
この時期は、下半期のスタートや秋の人事異動のタイミングと重なり、キャリアチェンジを考える人材が増加します。
また、年内に転職先を決めて、年明けから新しい環境でスタートしたいと考える求職者も多く存在します。
秋の転職市場は、以下のような特徴があります。
- 下半期開始や秋の人事異動をきっかけに転職を決意する
- 年内に次の職場を決めたいという意識が働く
- 年末年始を挟むため、選考スケジュールに余裕を持つ必要がある
- 企業側も来期の体制構築に向けて採用を強化する時期
これら3つの時期を総合すると、中途採用市場は概ね年に3回の波があることが分かります。
| 時期 | 求職者の動き | 主な転職理由 | 入社希望時期 |
| 1〜3月 | 最も活発 | 冬のボーナス後、年度の区切り | 4月入社 |
| 6〜7月 | やや活発 | 夏のボーナス後、上半期評価 | 7〜10月入社 |
| 9〜11月 | 活発 | 下半期開始、秋の人事異動 | 1月入社 |
ただし、これらの時期以外が全く動かないわけではありません。
通年で転職活動をしている求職者も一定数存在しますし、特に専門性の高い職種やハイクラス人材は、時期に関係なく転職機会を探している傾向があります。
また、業界や職種によっても求職者の動きには違いがあります。
たとえば、IT業界やベンチャー企業では、年度という概念よりもプロジェクト単位で人材の流動性が高く、比較的通年で求職者が動いているといえます。
逆に、伝統的な大企業や公的機関からの転職を考える人材は、年度の区切りを重視する傾向が強いです。
求職者が動く時期を理解することで、応募が集まりやすいタイミングで求人を出すことができ、採用活動の効率を大きく向上させることができます。
企業が動く月(1・7・10月/2〜3月に採用強化)
求職者が動く時期がある一方で、企業側が採用活動を強化するタイミングにもパターンがあります。
企業の採用活動は、事業計画や組織体制の見直しのタイミングと密接に関連しています。
まず、1月は多くの企業が採用活動を本格化させる月です。
新年度の4月入社に向けて、1月から求人を出し始める企業が多く、年間で最も求人数が増える時期の一つとなります。
特に、年度末の3月までに採用を決定し、4月から新メンバーを迎え入れたいという企業のニーズが高まります。
この時期は求職者も多く動くため、需給が一致する一方で、競合他社との人材獲得競争も最も激しくなる時期です。
優秀な候補者には複数のオファーが集中するため、選考スピードや条件面での競争力が求められます。
次に、7月も企業が採用を強化する月です。
上半期が終了し、下半期の事業計画に基づいて人員配置を見直すタイミングで、追加採用や欠員補充のニーズが高まります。
また、新卒採用が一段落し、人事部門のリソースを中途採用に振り向けられるようになることも、この時期に採用活動が活発化する理由の一つです。
7月に採用活動を始めることで、9月や10月の下半期開始に合わせて人材を確保することができます。
さらに、10月も企業が動き出す重要な月です。
多くの企業では10月が下半期のスタートであり、組織体制を強化するために採用活動を開始します。
また、来年度の事業計画を見据えて、年明けや新年度に向けた採用準備を始める時期でもあります。
10月から採用活動を始めることで、年内または年明けの1月入社を目指すことができ、年度末の繁忙期を避けて計画的に人材を確保することが可能です。
そして、2月から3月は採用活動が最もピークに達する時期です。
4月入社に向けて、最後の採用チャンスとして多くの企業が積極的に動きます。
この時期は求人数が年間で最も多くなり、求職者にとっては選択肢が豊富な一方で、企業にとっては最も競争が激しい時期となります。
2月から3月の採用市場の特徴は以下の通りです。
- 年間で最も求人数が多く、競争が激化する
- 4月入社という明確なゴールに向けて、スピード選考が求められる
- 優秀な候補者は複数の企業から内定を得ている可能性が高い
- 条件面や企業の魅力で差別化を図る必要がある
企業が採用を強化する時期をまとめると、以下のようになります。
- 1月:新年度(4月)入社に向けた採用活動の本格化
- 7月:下半期開始に向けた採用強化、新卒採用の終了
- 10月:下半期スタートと来年度準備のための採用開始
- 2〜3月:4月入社に向けた最終的な採用ピーク
これらの時期に採用活動を行うメリットは、求職者の動きと企業の採用ニーズが一致するため、応募が集まりやすいことです。
しかし同時に、競合他社も採用を強化しているため、人材獲得競争が激化するというデメリットもあります。
一方で、これらの時期以外にあえて採用活動を行う戦略もあります。
たとえば、5月や8月、12月といった比較的閑散期に求人を出すことで、競合が少ない中でじっくりと候補者と向き合うことができます。
また、通年採用の体制を整えることで、優秀な人材が市場に現れたタイミングを逃さず、機動的に採用活動を展開することも可能です。
企業が動く時期を理解した上で、自社の状況に合わせて、繁忙期に参戦するか、あえて閑散期を狙うかを戦略的に判断することが重要です。
時期別の募集戦略

繁忙期に勝つ施策(迅速選考・差別化・スカウト併用)
1月から3月、そして2月から3月の採用ピーク時期は、最も多くの求職者が動く一方で、企業間の競争も最も激しい時期です。
この繁忙期に優秀な人材を獲得するためには、明確な戦略が必要です。
まず最も重要なのが、迅速な選考プロセスの構築です。
繁忙期の求職者は、複数の企業に応募し、並行して選考を進めているケースがほとんどです。
そのため、書類選考から面接、内定までのスピードが遅いと、優秀な候補者は他社に流れてしまいます。
迅速選考を実現するための具体的な施策は以下の通りです。
- 書類選考は応募から3営業日以内に結果を通知する
- 一次面接の日程は候補者の希望を最優先し、柔軟に対応する
- 面接から次のステップへの連絡は24時間以内に行う
- 最終面接から内定までの期間を1週間以内に短縮する
- オンライン面接を積極的に活用し、日程調整の柔軟性を高める
ある中堅IT企業では、書類選考から内定まで平均2週間かかっていたプロセスを1週間に短縮したところ、内定承諾率が65%から85%に向上しました。
候補者からは「対応が早く、本気度を感じた」というフィードバックが多く寄せられたといいます。
次に重要なのが、競合他社との差別化です。
繁忙期には同じような求人が大量に出回るため、求職者の目に留まり、応募してもらうためには明確な差別化ポイントが必要です。
差別化のポイントとして効果的なのは以下の要素です。
- 具体的な業務内容とプロジェクト事例の提示
- キャリアパスや成長機会の明確化
- リモートワークやフレックスなど柔軟な働き方の提示
- 独自の福利厚生や待遇面での優位性
- 企業のビジョンや社会的意義の訴求
- 社員インタビューや職場の雰囲気が分かるコンテンツ
特に、抽象的な表現ではなく、具体的な数字や事例を盛り込むことで、求職者の興味を引くことができます。
たとえば、「成長できる環境」ではなく「入社3年で課長に昇進した事例が5件、年間の研修予算は一人あたり50万円」といった具合に、定量的で検証可能な情報を提供することが重要です。
さらに、繁忙期には待ちの姿勢だけでなく、攻めの採用手法を併用することが効果的です。
具体的には、ダイレクトリクルーティング(スカウト)を活用し、企業側から候補者に直接アプローチする手法です。
スカウト採用のメリットは以下の通りです。
- 転職顕在層だけでなく、転職潜在層にもアプローチできる
- 求人広告を見ていない優秀な人材にリーチできる
- 企業からの直接アプローチにより、候補者の関心を引きやすい
- 競合他社が見つけていない人材を発掘できる可能性がある
スカウトを効果的に活用するためには、候補者一人ひとりに合わせたパーソナライズされたメッセージを送ることが重要です。
テンプレート的な一斉送信メッセージではなく、候補者の経歴やスキルを踏まえた上で、「なぜあなたに興味を持ったか」「どのような役割を期待しているか」を具体的に伝えることで、返信率が大きく向上します。
ある企業では、スカウトメッセージを候補者ごとにカスタマイズしたところ、返信率が5%から20%に向上したという事例もあります。
また、繁忙期には内定者フォローも重要な施策となります。
優秀な候補者は複数の内定を獲得している可能性が高いため、内定を出した後も丁寧なフォローを続け、自社を選んでもらうための努力が必要です。
内定者フォローの具体策としては以下が挙げられます。
- 内定後すぐに経営層や配属予定部署の責任者との面談機会を設ける
- 職場見学や現場社員との交流機会を提供する
- 入社前の不安や疑問に迅速かつ丁寧に対応する
- 定期的な連絡を通じて関係性を維持する
- 条件面での懸念があれば、可能な範囲で調整を検討する
繁忙期の採用戦略をまとめると、以下の表のようになります。
| 施策 | 具体的な内容 | 期待される効果 |
| 迅速選考 | 書類選考3日以内、面接24時間以内の連絡 | 他社への流出防止 |
| 差別化 | 具体的な数字と事例での訴求 | 応募意欲の向上 |
| スカウト併用 | パーソナライズされた直接アプローチ | 潜在層の発掘 |
| 内定者フォロー | 経営層面談、職場見学の実施 | 内定承諾率の向上 |
繁忙期は競争が激しい分、戦略的に動いた企業が優秀な人材を獲得できる時期でもあります。
これらの施策を組み合わせることで、競合に勝ち、採用成功の確率を高めることができます。
閑散期の攻略(前倒し掲載・長期露出で可視化)
4月から5月、8月、12月といった閑散期は、求職者の動きが鈍く、応募が集まりにくい時期です。
しかし、この時期にも有効な採用戦略が存在します。
閑散期の最大のメリットは、競合他社が少ないため、出した求人が目立ちやすいことです。
また、この時期に転職活動をしている求職者は、明確な目的意識を持った計画的な転職者である可能性が高いという特徴があります。
閑散期の採用戦略として最も有効なのが、前倒し掲載です。
たとえば、4月入社を目指すのであれば、通常は1月から2月に求人を出すのが一般的ですが、あえて前年の11月や12月から求人を出し始めることで、競合が少ない時期に候補者との接点を作ることができます。
前倒し掲載のメリットは以下の通りです。
- 競合が少ない時期に求人を目立たせることができる
- じっくりと候補者と向き合う時間的余裕がある
- 繁忙期に向けて計画的に転職活動を始める優秀な人材にリーチできる
- 選考プロセスを丁寧に進めることで、ミスマッチを防げる
ある製造業の企業では、例年2月から採用活動を始めていましたが、前年の11月から前倒しで求人を出したところ、応募数は減少したものの、採用した人材の質が向上し、入社後の定着率が大幅に改善したという事例があります。
閑散期には応募数が少ないため、量ではなく質を重視した採用ができるのです。
次に重要なのが、長期露出による可視化です。
閑散期は求職者が少ないため、短期間で大量の応募を集めることは難しいですが、長期間にわたって求人を掲載し続けることで、潜在的な転職希望者の目に触れる機会を増やすことができます。
長期露出の戦略としては、以下のような施策が効果的です。
- 求人サイトに3ヶ月以上の長期プランで掲載する
- 自社採用サイトを充実させ、SEO対策を強化する
- SNSで定期的に採用情報を発信し、認知度を高める
- 社員紹介(リファラル採用)を促進し、社員ネットワークを活用する
- 業界イベントやセミナーへの参加を通じて、潜在層と接点を作る
長期露出の目的は、すぐに応募してもらうことではなく、企業の存在を認知してもらい、転職を考えたときに候補に入れてもらうことです。
特に、自社採用サイトの充実とSEO対策は、閑散期に取り組むべき重要な施策です。
「○○ エンジニア 求人」「○○ 営業 転職」といったキーワードで検索した際に、自社の採用サイトが上位に表示されるようにすることで、能動的に転職先を探している求職者に自然にリーチすることができます。
また、閑散期は採用体制の見直しや改善に取り組む絶好の機会でもあります。
繁忙期は日々の選考対応に追われて、採用プロセスの改善や求人内容のブラッシュアップに時間を割けないことが多いですが、閑散期であれば余裕を持って以下のような取り組みができます。
- 求人原稿の内容を見直し、より魅力的な表現に改善する
- 選考プロセスを見直し、無駄なステップを削減する
- 面接官のトレーニングを実施し、面接の質を向上させる
- 採用データを分析し、効果的なチャネルや施策を特定する
- 内定者や入社者へのアンケートを実施し、改善点を洗い出す
さらに、閑散期にはターゲット層を広げることも有効な戦略です。
繁忙期には理想の人材像に完全にマッチする候補者を求めがちですが、閑散期には応募数が少ないため、少し条件を緩和したり、未経験者や異業種からの転職者も検討することで、応募の間口を広げることができます。
実際、異業種からの転職者が新しい視点をもたらし、組織に良い刺激を与えたという事例は数多く存在します。
閑散期の採用戦略をまとめると、以下のようになります。
- 前倒し掲載で競合が少ない時期に候補者との接点を作る
- 長期露出で潜在層の認知度を高める
- 採用体制の改善に時間を使う
- ターゲット層を広げて応募の間口を拡大する
- 質を重視したじっくりとした選考を行う
閑散期は「応募が集まらない時期」ではなく、戦略的に動くことで競合に差をつけられる時期と捉えることが重要です。
逆算スケジュールと実務

求人開始から入社までの目安期間(約1〜3か月)
採用活動を成功させるためには、入社希望時期から逆算してスケジュールを立てることが不可欠です。
中途採用では、求人を出してから実際に入社するまでに一定の期間が必要であり、この期間を正確に把握しておくことが重要です。
一般的に、求人開始から入社までには約1か月から3か月程度の期間が必要とされています。
ただし、この期間は職種や業界、企業規模、選考プロセスの複雑さによって大きく変動します。
まず、採用プロセス全体の流れを整理しましょう。
標準的な中途採用のフローは以下のようになります。
- 求人掲載開始:求人サイトや自社サイトに求人情報を掲載
- 応募受付:応募書類の受領と確認(掲載から1〜2週間)
- 書類選考:履歴書・職務経歴書の審査(応募から3〜5日)
- 一次面接:現場責任者や人事担当者による面接(書類選考通過から1〜2週間)
- 二次面接:部門長や役員による面接(一次面接から1〜2週間)
- 最終面接:経営層による面接(二次面接から1週間)
- 内定通知:採用決定と条件提示(最終面接から3〜7日)
- 内定承諾:候補者からの返答(内定通知から1〜2週間)
- 退職交渉:現職での退職手続き(内定承諾から1〜2か月)
- 入社:新しい会社でのスタート
このプロセスを踏まえると、最短でも求人掲載から入社まで1か月半から2か月、通常は2か月から3か月程度の期間を見込んでおく必要があります。
特に時間がかかるのが、内定承諾後の退職交渉期間です。
多くの企業では、退職の申し出から実際の退職日まで1か月から2か月の期間を要求されます。
法律上は2週間前の退職届で退職できますが、業務の引き継ぎや後任者の手配を考慮すると、1か月から2か月程度が現実的です。
また、管理職や専門職など、重要なポジションにいる人材ほど、退職までの期間が長くなる傾向があります。
採用プロセスの各段階にかかる期間を表にまとめると、以下のようになります。
| 段階 | 所要期間 | 備考 |
| 応募受付 | 1〜2週間 | 求人掲載後の応募集約期間 |
| 書類選考 | 3〜5日 | 応募から結果通知まで |
| 一次面接 | 1〜2週間 | 日程調整と面接実施 |
| 二次面接 | 1〜2週間 | 日程調整と面接実施 |
| 最終面接 | 1週間 | 日程調整と面接実施 |
| 内定通知 | 3〜7日 | 社内承認と条件調整 |
| 内定承諾 | 1〜2週間 | 候補者の検討期間 |
| 退職交渉 | 1〜2か月 | 現職での引き継ぎ |
これらを合計すると、最短でも約1.5か月、通常は2〜3か月程度となります。
ただし、この期間を短縮することも可能です。
選考プロセスを簡素化し、一次面接と二次面接を統合したり、オンライン面接を活用して日程調整の柔軟性を高めたりすることで、1か月程度で入社まで完結させるスピード採用も実現できます。
実際、IT業界やベンチャー企業では、応募から内定まで2週間、入社まで1か月という超高速採用を実施している企業もあります。
ただし、スピードを重視しすぎると、候補者の見極めが不十分になったり、候補者に焦りを感じさせて辞退につながるリスクもあるため、バランスが重要です。
逆に、選考プロセスが長引きすぎると、優秀な候補者が他社に流れてしまうリスクが高まります。
応募から内定まで2か月以上かかる場合、候補者の半数以上が他社に流れるというデータもあります。
採用スケジュールを立てる際には、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 入社希望時期から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組む
- 各選考段階の期間を明確にし、社内で共有する
- 候補者に選考フローと所要期間を事前に伝える
- 遅延が発生した場合は、候補者に速やかに連絡する
- 退職交渉期間を考慮し、柔軟な入社日設定を検討する
求人開始から入社までの期間を正確に把握し、逆算してスケジュールを立てることで、計画的な採用活動を実現できます。
期別モデル(4月入社/9月入社の逆算計画)
具体的な入社時期を例に、逆算スケジュールの立て方を見ていきましょう。
ここでは、最も一般的な4月入社と、下半期開始の9月入社のケースを取り上げます。
4月入社を目指す場合の逆算スケジュール
4月1日入社を目指す場合、最も重要なのは1月中には内定を出しておくことです。
内定から入社までに退職交渉期間として2か月を見込むと、1月末に内定を出せば、3月末退職・4月1日入社というスケジュールが実現できます。
4月入社の理想的なスケジュールは以下の通りです。
- 11月下旬〜12月:求人原稿の準備と求人掲載開始
- 12月〜1月上旬:応募受付と書類選考
- 1月中旬:一次面接の実施
- 1月下旬:二次・最終面接の実施
- 1月末〜2月初旬:内定通知と内定承諾
- 2月〜3月:退職交渉と入社準備
- 4月1日:入社
このスケジュールの利点は、年末年始の比較的競合が少ない時期に求人を出せることです。
また、1月は求職者が最も動く時期であるため、応募が集まりやすいというメリットもあります。
ただし、年末年始を挟むため、選考スケジュールの調整には注意が必要です。
12月後半は候補者も企業も年末の繁忙期に入るため、面接日程の調整が難しくなる可能性があります。
そのため、できれば12月中旬までに書類選考を終え、年明けすぐに面接をスタートできる体制を整えておくことが理想的です。
もし、より確実に4月入社を実現したい場合は、さらに前倒しして10月から求人を出し始めるという選択肢もあります。
10月から動き始めれば、11月から12月にかけて選考を進め、12月中に内定を出すことも可能です。
これにより、退職交渉に3か月の余裕を持たせることができ、候補者にとっても無理のないスケジュールとなります。
9月入社を目指す場合の逆算スケジュール
下半期の開始となる9月入社を目指す場合は、6月中には内定を出しておくことが理想的です。
9月入社の理想的なスケジュールは以下の通りです。
- 5月:求人原稿の準備と求人掲載開始
- 5月下旬〜6月上旬:応募受付と書類選考
- 6月中旬:一次面接の実施
- 6月下旬:二次・最終面接の実施
- 6月末〜7月初旬:内定通知と内定承諾
- 7月〜8月:退職交渉と入社準備
- 9月1日:入社
9月入社のメリットは、夏のボーナスを受け取った求職者が動き出す時期と重なることです。
6月下旬から7月にかけて転職活動を始める人材にアプローチできるため、応募を集めやすいタイミングといえます。
また、新卒採用が一段落した時期でもあるため、人事部門のリソースを中途採用に集中できるというメリットもあります。
ただし、7月から8月は夏季休暇シーズンでもあるため、退職交渉や入社準備がスムーズに進まない可能性があります。
特に、候補者が夏季休暇を取得する場合や、現職の引き継ぎ相手が休暇中の場合など、スケジュールが遅れるリスクを考慮しておく必要があります。
そのため、9月入社を確実にするためには、5月から動き始め、6月中旬までには内定を出すというスケジュールが理想的です。
両ケースに共通する逆算スケジュールのポイントは以下の通りです。
- 入社日から2〜3か月前には内定を出す
- 内定から1〜2週間前には最終面接を終える
- 最終面接から2〜3週間前には一次面接を開始する
- 一次面接から1〜2週間前には求人掲載を開始する
つまり、入社希望日の3〜4か月前には採用活動をスタートさせることが、余裕を持ったスケジュールとなります。
逆算スケジュールを立てる際の注意点として、以下が挙げられます。
- 年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇などの長期休暇を考慮する
- 候補者の退職交渉に予想以上に時間がかかる可能性を想定する
- 社内の承認プロセスに必要な期間を事前に確認する
- 繁忙期と閑散期の違いを理解し、応募数の見込みを調整する
- 選考途中での辞退や内定辞退のリスクを考慮し、複数の候補者を並行して進める
また、業界や職種によっても適切なスケジュールは異なります。
たとえば、専門性の高いエンジニアやコンサルタントなどは、転職活動に時間をかける傾向があるため、より長期的なスケジュールを見込む必要があります。
逆に、営業職やバックオフィス職など、比較的転職が活発な職種では、短期間で採用が決まるケースも多くあります。
逆算スケジュールを立てることで、計画的に採用活動を進め、入社希望時期に確実に人材を確保することができます。
まとめ
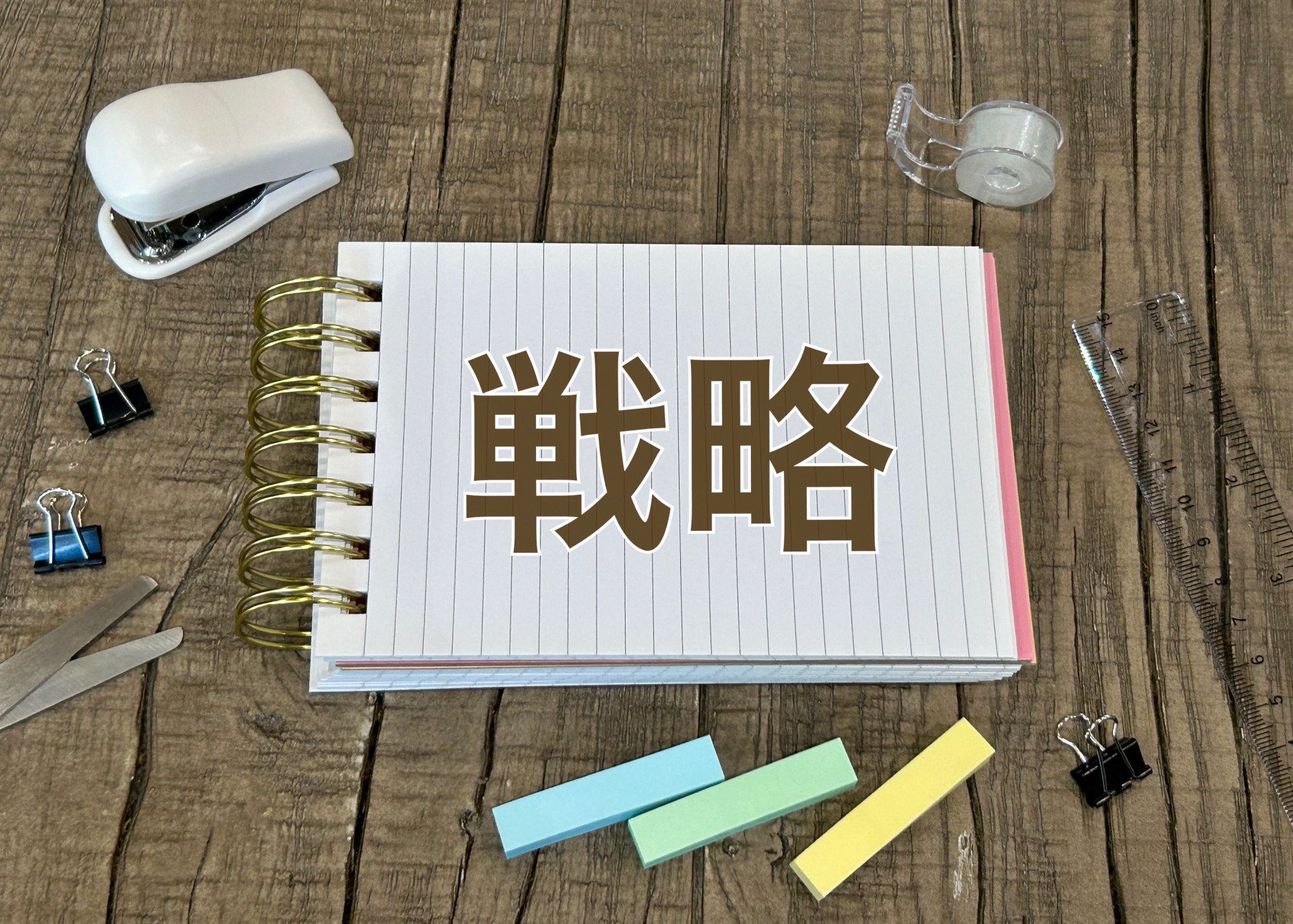
中途採用を成功させるためには、時期を見極めた戦略的なアプローチが不可欠です。
本記事では、求職者が動く時期と企業が採用を強化する時期の全体像を明らかにし、繁忙期と閑散期それぞれに適した募集戦略を解説してきました。
求職者が最も動くのは1月から3月、6月から7月、9月から11月の年3回であり、特に1月から3月は年間で最も活発な時期です。
企業側も1月、7月、10月に採用活動を本格化させ、2月から3月がピークとなります。
繁忙期には、迅速な選考プロセス、明確な差別化、スカウトの併用、丁寧な内定者フォローといった競合に勝つための施策が求められます。
一方、閑散期には、前倒し掲載や長期露出による可視化、採用体制の改善など、戦略的に動くことで競合に差をつけられる機会があります。
また、入社希望時期から逆算したスケジュール管理も重要です。
求人開始から入社までには通常2か月から3か月程度の期間が必要であり、4月入社なら1月までに、9月入社なら6月までに内定を出すことが理想的です。
中途採用市場の時期特性を理解し、自社の状況に合わせた最適なタイミングで採用活動を展開することで、限られた予算と時間の中で最大限の成果を上げることができます。
ぜひ本記事の内容を参考に、戦略的な採用活動を実践してください。
採用活動にお困りの方は株式会社アクセスへご相談ください。
株式会社アクセスは、名古屋・愛知県内の求人専門の広告代理店として、これまでに累計10,261社以上の企業様の採用活動を支援してまいりました。
中途採用の時期戦略や採用スケジュールの立案はもちろん、効果的な求人媒体の選定から採用サイトの制作、採用動画の制作まで、採用活動のあらゆる場面でお客様をサポートいたします。
「いつ求人を出せば良いか分からない」「応募が集まらない」「採用スケジュールの立て方が分からない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
特に、Indeedをはじめとする求人媒体を活用した採用支援では、時期に応じた最適な運用戦略をご提案し、多くの成功事例を生み出しています。
採用のプロフェッショナルが、貴社の課題や希望入社時期に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。
24時間求人掲載を受け付けており、いつでもお問い合わせいただけます。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-15-5592(受付時間 9:00〜18:00 土日祝日定休)までお電話いただくか、弊社ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。
採用成功事例やお役立ち情報も公開しておりますので、ぜひ弊社ウェブサイトもご覧ください。
貴社の採用活動を成功に導くため、株式会社アクセスが全力でサポートいたします。